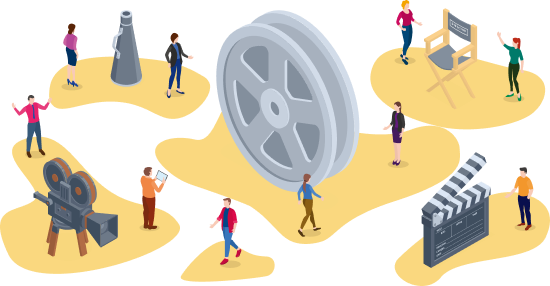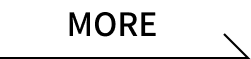視覚と聴覚の両方に障害を抱える盲ろう者として世界初の大学教授となり、現在も東京大学で教鞭をとる福島智氏。2003年には米国タイム誌の「アジアの英雄」にも選ばれ、国境を越えて大きな注目を集める人物だ。9歳で失明し、18歳で聴覚も失うという困難に見舞われながらも、考える力を“武器”に決して希望を捨てなかったまさに努力の人……。だがその背景には、母の深い愛情とたくましくも涙ぐましい支えがあった。
そんな母と子の半生をリアルに描き上げた映画『桜色の風が咲く』が11月4日(金)より全国公開された。手掛けたのは、『最後の命』(2014)や『パーフェクト・レボリューション』(2017)で知られる松本准平監督だ。東京大学で建築を学びながら吉本総合芸能学院(NSC)に入学し、芸人にも挑戦したことがあるという異色の経歴の持ち主でもある。今回のインタビューでは、福島氏との出会いから作品完成までの道のり、12年ぶりに主演を務めた小雪のプロ意識、さらには映画監督として自身の目指す未来について語ってもらった。

あらすじ:教師の夫・正美(吉沢悠)とともに、関西の町で三人の息子を育てていた令子(小雪)。末っ子の智(田中偉登/たなか・たけと)は幼少期に視力を失ってしまうも、家族に支えられながら天真爛漫に成長する。高校生になると、1人で東京の盲学校に進学。母の心配をよそに、学校生活を謳歌していた。ところが、18歳のときに聴力も失い、智は暗闇と無音の宇宙空間に放り出されたような孤独を味わう。そんななか、令子が日常のなかで生み出した“指点字”という新たなコミュニケーションが立ち上がるきっかけを与えることに……。
●27稿にまでおよんだこだわりの脚本作り
―福島智さんとは、前作『パーフェクト・レボリューション』の上映会で対談相手として出会われたのが最初だったそうですが、そのときの印象を教えてください。
松本監督:それまで盲ろうの方とお会いしたことがなかったので、指を点字タイプライターに見立ててコミュニケーションを取る“指点字(点字タイプライターのキーの配置をそのまま人の指に当てはめ、手と手で直接会話する方法)”というものがあることも知らず、まずはそれに驚きました。たぶん本作も、音声ガイドにまとめたものを指点字で理解されていると思うのですが、作り手の意図を深く読み取っており、作品に対してもいろんなご指摘と聡明なご意見をいただいたので、「この人はとんでもない人だな」と。不思議な洞察力がある方だと感じて、福島さんに興味が湧きました。


―映画化するうえで、ご本人からはアドバイスなどもありましたか?
松本監督:とにかく脚本は随時読みたいとおっしゃっていたので、頻繁にやりとりをさせていただきました。なかでも僕の想像と盲ろう者との現実に乖離(かいり)していたところがあったため、そこの穴埋めをしたかったんだと思います。最終的には脚本も27稿にまで及んだので、福島さんの意見はかなり反映しました。
―具体的にどういった部分に修正が入ったのですか?
松本監督:福島さんは、自分の身に起こった悲劇に対して感情的になったり、暴れたりということはなさらなかったようですが、過去にドラマ化された時、演出上、そういう描写があったと聞きました。ただ、うまく行かなくて暴れれば済むような次元の話でもないし、それは自分とはまったく違うから必要以上に八つ当たりするような描き方はやめて欲しいと。僕も嘘はつきたくないと思っていたので、福島さんに事実を確認しながら、そのままを描くように心がけました。
●小雪のプロフェッショナルな姿勢に感服
―今回、母親役を演じた小雪さんの存在感は大きかったと思いますが、キャスティングした経緯は?
松本監督:実は、小雪さんのマネージャーさんがこの映画の話をどこかで聞きつけ、「この役を小雪にどうですか?」と声をかけてくださったのがきっかけです。ただ、小雪さんにはお母さんよりもモデルのようなイメージが強かったので、最初はどうだろうと思っていました。そんななか、実際にお会いして話をしていくと、彼女からは母親の愛情がにじみ出ていて、まさにお母さんという印象。しかも、日々の小さなことに対して丹念に向き合い、日常を大切にされている方なので、そういうところもでバッチリだなと感じ、あとは大船に乗ったつもりでいました。

―現場に入ってからの小雪さんの様子はいかがでしたか?
松本監督:小雪さんには、つねに驚かされていた気がします。泣く芝居では本当に泣いていましたし、僕がどのようにすればちゃんと描けるだろうかと悩んでいた母親による愛の在り方もちゃんとカメラの前で提示してくださいました。あとは、とにかく覚えるのが難しいと言われている指点字を1週間ほどで習得されていたのもすごかったです。
―子役とのやりとりも、本物の親子のような佇まいはさすがでした。
松本監督:特に、智の幼少期を演じてくれた1歳の子役はお母さんから離れるとわんわん泣いて大変でしたが、カメラに映っていないところでも小雪さんがずっと抱いてくださっていたので、小雪さんにだけはなついていました。やっぱり子どもにはわかるんですね。子役に関しては、「よーい、ハイ」と声をかけずに、小雪さんにタイミングを見計らってもらいながらカメラを回していたので、かなり助けていただきました。

―演出面に関しては、どういったことを意識されていましたか?
松本監督:もともと僕はテストも段取りもあまりしたくないタイプなのですが、小雪さんからも同じような意見があったので、基本的にテストはほぼ無しで進めました。というのも、僕はそのほうが役者さんという存在を丸ごと撮れると考えているからです。何テイクも続ければ芝居としては上手くなりますが、カメラに映るものとしては新鮮な驚きがなくなっていくのではないかなと思うので。もちろん膨大な回数を重ねることで別のフェーズに突入することはあるかと思いますが、そんな余裕はないですし。今回もこのような方法だったからこそ、キャストの生なものが撮れたのではないかと感じています。
●青年期を演じた田中偉登を福島氏も絶賛
―また、青年期の智を演じた田中偉登さんも素晴らしかったですが、オーディションではほぼ即決だったとか。どのようなところが決め手になったのでしょうか。
松本監督:最初のオーディションのときに、「どの瞬間でもいいから目が見えない人の生活を演じて欲しい」とお願いしました。だいたいの人は、ご飯を食べているときとか、料理をしているときでしたが、田中くんだけは「シャワーを浴びたいんですけど、いいですか?」と。まずはそこでつかまれましたね。そのあともあるシークエンスを演じてもらったら、1回で一気に感情を入れて涙を流す芝居をしていて、それを見たときに彼は押しかかってくる重圧を跳ね返す気持ちとエネルギーがある人だと感じました。存在感も含めて智とリンクするものが見えましたし、見事に演じてくれるだろうと思えたのが大きかったです。

―福島さんからキャスティングに関する要望などはありましたか?
松本監督:こういう人がいいみたいなことは特になかったですが、福島さんが田中くんのことをネットで調べたときに「得意なことはコーラをがぶ飲みすること」と書かれていたそうで、それを知って「この人はアホやな(笑)。いいと思いますよ」と言っていました。福島さんもユーモアがある方ですが、同じ関西人としても親近感を覚えられたのかもしれないですね。
―実際、福島さんから田中さんにアドバイスされるようなこともあったのでしょうか。
松本監督:一緒に時間を過ごしてもらうのが一番いいと思ったので、事前に田中くんとほかの役者さんを福島研究室に預けることにしました。2か月近く通ってもらうなかで指点字を教わったり、盲ろう者になったときの気持ちを話してもらったりしたと聞きました。僕は演技というのは役者が誰かに「なろう」と思ったらできないものだと考えていて、それよりも「役と親しくなって心を開き合うこと」が一番大事だと思っています。今回は、田中くんが福島さんの持っているエッセンスをゆっくりと時間をかけて体に染み込ませていたように感じました。

―本作を通して、監督自身に影響を与えたようなことがあれば教えてください。
松本監督:撮影の前は、プライベートなことで悩みもありましたが、小雪さんが演じる母や妻として在り方を目の当たりにして、やっぱり女性は偉大だと感じました。妻と些細なことでケンカすることもありますが、彼女が背負っているものや子どもに対する思いを考えたら、そんな小さいことはどうでもいいんじゃないかなと。小雪さんの存在感によってそれをまざまざと見せていただいたので、この現場ではたくさんのことを教えてもらったと思います。ただ、妻はウディ・アレンの映画しか観ないので、僕の作品は観てくれないですが(笑)。
●建築でもない、お笑いでもない、映画監督こそ天職?!
―監督自身についてもお伺いしますが、子どもの頃は藤子・F・不二夫さんに憧れて漫画家を目指し、その後はダウンタウンの松本人志さんの影響で芸人を目指しながら東京大学で建築を学んでいたとか。そこからどのようにして映画監督の道に進まれたのですか?
松本監督:芸人を辞めたあと、NPO法人を設立した友達から成人式で流す若者向きの映画を作りたいから監督をして欲しいと頼まれたのが最初です。映画を勉強したことはありませんでしたが、僕がクリエイティブなことに興味があることを知っていたので誘ってくれたんだと思います。そのときに、芸人や建築よりも自分に向いているなと。そこから昔の映画を観て歴史を学び始め、面白い映画から刺激を受けてますますやってみたいと思うようになりました。そのあとは、映画を作るための時間を持つために大学院へ進み、修士論文と並行して、脚本を書いたり、自主映画を作ったりという生活を送ることに。卒業後は、インディーズで商業映画を撮る話も出ましたが、リーマン・ショックで立ち消えになり、それからテレビの制作会社で働きはじめました。

―ちなみに、どのあたりが自分には映画監督が向いていると?
松本監督:向いているかはどうかわかりませんが、僕は自分自身で表現するよりも、とにかく考えるのが好きな性格。芸人時代もネタを書くのは好きでしたが、自分でやろうとすると緊張して上手くできなかったですし、建築も模型を作るのが下手でセンスがありませんでしたから(笑)。それに比べると、映画監督は考えることがメインの仕事なので、いままでいろいろとやってきたなかで自分にとっては一番やりやすいと感じました。
―今後はどういった作品を手掛けていきたいとお考えですか?
松本監督:あまりにも自分からかけ離れたものをテーマにしても、嘘っぽい作品、信じてもらえない作品になってしまうと思うので、まずは「自分の心に響くかどうか」を大事にしたいと考えています。例えば、僕はドストエフスキーが大好きなんですが、多面的に世界を提示しながら重いテーマであっても大衆作家としての面白さも持ち合わせていると思うんです。僕は小さい頃からクリスチャンとして育ってきたこともあり、神の存在と不在についてつねに意識しながら生きているのですが、ドストエフスキーはそれをテーマに、良心の有無とか、人間の内面にまで落とし込んでいる。そこにすごく惹かれるんですよね。大袈裟なことを言うようですが、そういうドストエフスキーの背中をつねに追いかけながら映画を作り続けていけたらと思います。
―これから映画を通して伝えたいことや映画監督としての理想像があれば、お聞かせください。
松本監督:僕は映画に関しては独学ですし、考え方のベースがキリスト教なので、日本映画特有の“フェティシズム”がわからないところがあります。でも、そもそも自分が描きたいものを変えることはできませんし、どんどん逸脱していってもいいのかなとは思っています。いつかそれだからよかったのだ、と言ってもらえるように、いろんな挑戦をしたいですね。映画作りはお金もかかりますし、たくさんの方々の支えがなければ成り立たないものですが、だからこそ、死ぬまで作り続けることができたら最高です。(取材・文:志村昌美 写真:坂田正樹)

映画『桜色の風が咲く』は11月4日(金)よりシネスイッチほか全国公開中
文部科学省選定(青年・成人向き/2022年10月19日選定)
©THRONE / KARAVAN Pictures