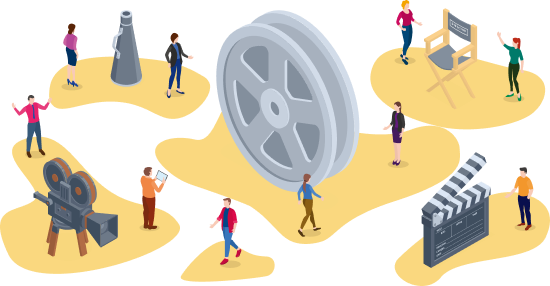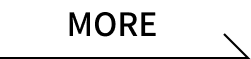映画『友だちのパパが好き』『クソ野郎と美しき世界』などで知られる山内ケンジ監督が、コロナ禍収束後の日本を舞台に、孫を切望する姑、そのプレッシャーに晒されながら暮らす若夫婦の“二世帯家族”の姿を赤裸々に描いた最新映画『夜明けの夫婦』がいよいよ本日より劇場公開される。
今でこそインディーズ映画や小劇場を主戦場に活躍する山内監督だが、かつては、日清食品の「UFO仮面ヤキソバン」やソフトバンクの「白戸家」など、CMディレクター、プランナーとしてお茶の間を賑わせていた広告界のヒットメーカー。そんな彼が、40歳を過ぎて、なぜ真逆ともいえる世界に飛び込んでいったのか。本作への熱い思いとともに、その経緯を聞いた。

本作のあらすじ:コロナ禍も一応の終焉を迎えた日本のとある町。さら(鄭亜美/チョン・アミ)は夫・康介(泉拓磨)の家で彼の両親と一緒に暮らしている。ある日、義理の母・晶子(石川彰子)が「そろそろ子供は?作らないの?」と遠慮がちに聞いてきた。だが、パンデミックの間、さらと康介は、これまで以上に長い時間を過ごしたのにセックスレスになってしまい、しかも康介はほかの女性と浮気している様子。一方の晶子は、コロナで年老いた母を亡くしたこともあり、呑気な夫(岩谷健司)をよそに命について深く考える毎日。どうしても孫の顔を見たいという欲求で精神的に不安定になっていた…。
「結局、何が言いたかったんだろ?」みたいな映画が理想
――二世帯夫婦のめくるめく思いを対比させながら描いた脚本がとても面白かったです。どのように着想されたのか教えていただけますか?
山内監督:演劇の場合、最初に主要キャスト、次にタイトルを決めて、チラシを先に作ってから台本に取り掛かる、というのが僕のやり方なんですが、映画作りもその流れでずっとやってきました。だから今回も、「鄭亜美さん(平田オリザ主宰の青年団所属の舞台女優)を主演で何か撮りたい」というところから全てが始まっています。

――俳優を決める前にシノプシスみたいなものもなかったんですか?
山内監督:特にありません。鄭さんが決まった時点で全て動き出したという感じです。例えば今回は、彼女は他所から来たお嫁さん、それなら夫は泉拓磨さん、義理の親夫婦は岩谷健司さんと石川彰子さんがいいかな…という具合に、鄭さんを起点に決めていきました。また、コロナ禍での撮影で予算も極めて少なかったので、僕の実家を中心に撮影することもあらかじめ決めました。そうやって物理的な面をしっかり固めてから、二世帯同居にしようとか、子供を作る作らないの話にしようとか、ストーリーを考えていきました。

――この物語にふさわしい女優さんは誰か?ではなく、鄭さんを起点に全てが動いていくっていうところが面白いですね?
山内監督:鄭さんが30代半ばだったので、年齢的に仕事か子供かで悩むころかな?というのもありましたが、ちょうどそのころ、知り合いの舞台女優さんの間でベビーブームが起きたことも大きかったですね。映画の後半に本人たちがお子さんと一緒に出演していますが、こういうシーンは今しか撮れないなぁと思って。あとは、鄭さんが在日コリアンだったことも物語に影響しています。劇中、嫁に来たさらは、義理の両親に対してお父様、お母様という言い方をしていて、まるで昔の原節子のようなキャラクター。最初は昭和っぽい日本人のお嫁さんを想定していたんですが、鄭さんのバックボーンを生かした方が、本音をなかなか言えないとか、丁寧な言葉遣いになるとか、自然に出てくるので、そういう設定しました。まぁ、そんなことをグダグダと組み合わせていくうちにだんだんストーリーが出来上がっていったという感じですね。

――でも、結果的にはすごく良くまとまっていたと思います。山内監督としては思い通りの作品に仕上がったのですか?
山内監督:そうですね。前半は、子供を作る作らないとか、浮気してるとか、愛しているとか、結構ハッキリしたテーマで話は進んでいくんですが、後半からは、現実がだんだん捻じれてきて、妄想なのか、リアルなのかがわからなくなってくる…。そこが自分らしいというか、ポイントなんですね。「この映画は社会的なテーマを描いている」と胸を張って言える映画にはしたくなくて、「結局、何を言いたかったんだろ?」みたいな映画が僕の理想というか。コメディーを書いている訳ではないんですが、あまりにも切実すぎて笑うしかないみたいな…絶えずそういうものを作りたいなと思っています。

――ご実家を利用して撮影されたそうですが、予算的に厳しい面があっても、やはりオリジナル作品に今後もこだわっていくのでしょうか?
山内監督:有名な俳優さんを出さず、オリジナル脚本で勝負するっていうのは、なかなか難しいこと。それはもうわかっていることなので、どちらかを選択して行くしかないんですよね。プロデューサーと組んで原作ものとかスター俳優を起用した商業映画をやるか、あるいは、さらに低予算を極めて自分が本当に作りたいオリジナル作品を作り続けるか。もう、年齢的にも前者をやる機会はないので、僕は後者をもっと突き詰めてみたいなと思っています。今回は実家を撮影に使いましたし、あと知り合いのお店とか、知り合いの知り合いのお店とか。利用できるものは何でも利用するするという精神ですね。「大田原愚豚舎」という栃木の映像集団と知り合う機会があったんですが、彼らは少人数で映画を撮っていて、毎回、自宅とか喫茶店とか同じところが出てくるんです。物語はその都度違うけれど、撮影はいつも大田原という田舎町。その範囲で撮れるものを撮るんです。「なるほど、それでいいんだ」と。お金をかけず、自由にのびのびと映画が撮れることを彼らから学んだところもあります。


――ちなみに、映画のアイキャッチになっている「純粋社会派深刻喜劇」ってどういう意味ですか?
山内監督:僕が考えたんですが、うーん、よくわからないですね(笑)。まぁ、読んだ通りの意味です。
――舞台挨拶で「最後に監督、映画についてひと言」って言われたら、なんてアピールしますか?
山内監督:僕の映画はジャンル分けが難しいし、言語化するのも難しいので、とにかく観てもらうしかないですね。ただ、川端康成の小説を成瀬巳喜男監督が映画化した原節子、山村総主演の『山の音』』がベースなんです。息子のお嫁さんに義理のお父さんが淡い恋心を抱く話なんですが、この映画へのオマージュみたいなものが少しあります。
――なるほど…鄭さんが先か、オマージュが先かはわかりませんが、心のどこかにちゃんとベースがあったんですね。
CMディレクターから劇作家、映画監督に「自分の核がほしかった」
――山内監督はもともとCMディレクターでしたよね。広告業界ではヒットメーカーとして成功を収めていたのに、なぜこちらの世界を目指したのですか?
山内監督:まず、劇作家としてこの世界入ったんですが、CM業界から演劇に行く人って当時は珍しかったみたいですね。映画監督になる方は結構多かったようですが。もともと演劇を観るのが大好きで、80年代のブームですっかりハマってしまって、自分でも何か書きたいなと思っていたんですが、電通映画社に就職が決まり、その後フリーになってCMの仕事がどんどん忙しくなって。色々とタイミングが合わなかったんですね。そんな中で、コントを1本書いたりとか、短編を書いたりとか、そういうところから始めて、徐々に長編を書くようになっていったという感じです。
――そのころ、影響を受けた作品とか作家さんはいたんですか?
山内監督:学生時代は、当時、東京乾電池にいた岩松了さんとか、不条理演劇の別役実さんとか、二人の影響は大きかったですね。社会人になってからは、日常的な口語を演劇に一般化させた平田オリザさんの作品もずいぶん観ました。
――CM制作に関しては、何か不満はあったのですか?
山内監督:当時はネットもなく、みんなお茶の間でテレビを観ていた時代。反響が大きいと、
ヒットCMを期待されるようになって、次から次へとオファーが来るんです。ただ、やっているうちに、このまま続けて、この先自分はどうなるんだろう?と次第に考えるようになっていました。
――それはもう、演劇への思いが自分の上位に来てしまったという感じですか?
山内監督: 30代後半ぐらいからそう思うようになりました。CMのおかげでそこそこ裕福にはなれましたが、有名なヒットCMシリーズを作ると仕事が集中して何もできなくなっちゃうんです。それが何年も続いて、だんだん不安になってきたんですよね。自分自身がブームみたいな存在になってしまったから、いつかブームは去るだろうと。CMしかやっていないとなると、何も無くなった時にこれはやばいなと思いました。
――自分の「核」になるものが必要だなと感じたんですね?
山内監督:そうですね。自分でゼロから生み出すものをやっていかないと…という思いが強くなりましたね。ただ、やっぱりスタートが遅すぎました。初の長編『葡萄と密会』を書いたのが2004年、45歳くらいの時ですから。野田秀樹さんとか、松尾スズキさんとか、学生の頃から演劇をやってる同年代の人たちはもう大御所ですよ。それを考えると、僕は完全に遅れてきたっていう感じですね。

――スタートが遅かったとはいえ、劇作家、映画監督に転身して後悔はないですか?
山内監督:まったくありません。遅かったけれど、思い切って決断して良かったと思います。
――そんな山内監督から、これからエンタメ業界に入って来る方にアドバイスがあれば。
山内監督:本当に特殊な経緯を辿ってきたので、アドバイスすることなんて何もありません。ただ、経験から言えることは、若い時から映画や演劇をやりたい!という気持ちがあるなら、早めに、そこへ向かって突き進んでいくのが一番いいですよね。僕もそうしたかったけれど、それができなかったから、こんなに苦労してるわけで。ただ、インディーズで頑張ろうという子たちは、多分、お金がないのでバイト生活を強いられますよね。そうすると、社会に出る機会が失われ、視野の狭いオリジナル脚本しか書けなくなってしまう。豊富な社会経験があってこそのオリジナル脚本なので、そこが大きな課題だと思うんですよね。
(提供:バックヤード・コム 取材・文・写真:坂田正樹)
映画『夜明けの夫婦』は7月22日(金)より新宿ピカデリー、ポレポレ東中野、下北沢トリウッドほか全国順次公開