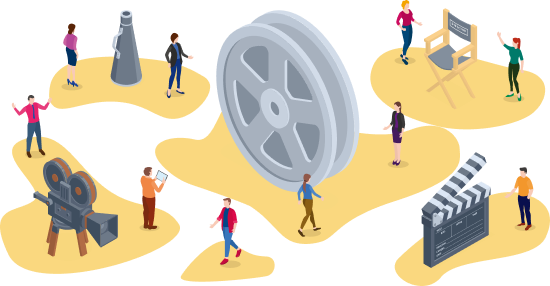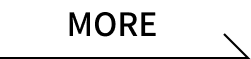「オラ、何にも悪いことしてねぇ。悪いことしたのは国だべ」――原発事故による全町避難で無人地帯となった福島県富岡町に一人で暮らす男性・ナオト(松村直登)さんの生きざまを捉え、世界を驚愕させたドキュメンタリー映画『ナオトひとりっきり』(15)。あれから8年、カメラはその後もナオトさんを追い続け、最新作『劇場版 ナオト、いまもひとりっきり』が公開された。

新型コロナウイルスの蔓延、復興五輪を掲げた東京オリンピック閉幕を経て、いまだ原発問題を抱えた福島の地は、メディアも人々の関心も薄れ、どこか「終わったこと」のように扱われている。だが、この映画の主人公・ナオトさんの暮らしは何も変わっちゃいない。原発事故後、人の人生を金で解決しようとする不条理、命を簡単に“処分”しようとする理不尽に納得できず、今も故郷・富岡町で動物たちとともに日々を過ごしている。
長年、彼を追い続けてきた中村真夕監督は映画のヒーローに例えて、「ナオトさんは福島のクロコダイル・ダンディー」と呼んでいるが、果たしてその実態は?彼のキャラクターを通して見えてきた「福島の今」を中村監督に聞いた。
●海外メディアのニュースでナオトさんの存在を初めて知った
――2013年から撮影をスタートさせたそうですが、そもそも、ナオトさんを撮ろうと思ったキッカケは何だったのでしょう。
中村監督:当時、フリーランスとして某テレビ局のニュース班にいたんですが、東日本大震災の被災地に関する番組制作に関わることが多くて、石巻に行ったり、女川に行ったり、いろんなところで取材していて、「何か私にもできることはないだろうか」とリサーチしていたら、海外のニュースメディアでナオトさんのことを知ったんです。

――海外メディアはナオトさんのことを何と伝えていたんですか?
中村監督:無人地帯に「動物のために残った人」みたいな感じで、動物愛護的観点で書かれているものが多かったですね。これを海外メディアのニュースで知ったわけですが、「この話、なぜ日本で伝えられていないのかな」とふと思って、上司に「ナオトさんをぜひ取材させてほしい」と提案したら、「君が健康被害にあっても責任を取れない」みたいなこと言われ却下されたんです。確か2013年の夏前ぐらいだったと思いますが、当時、帰還困難区域に残っているナオトさんに違法性を感じていたのかもしれないので、大手メディアはなかなか手が出せない案件なのかなと。一応、ナオトさんは許可を取って住んではいるんですけどね。だったら、「自己責任で、一人で行ってきます、そして自分の映画として制作します!」と言って、メディアを通さずフリーの仕事として撮影を始めました。

――「自分で撮りたい!」と思わせてくれたのがナオトさんだったということですか。
中村監督:テレビ局で番組制作に携わっていたこと、そしてナオトさんとの出会いはもちろんですが、実は私の父の故郷である福井県と境遇が似ていたことも大きかったです。原発も14機ありますしね。本作の冒頭に出てくる海は、昔、父に連れられて泳ぎを練習させられた若狭湾なんですが、原発が見える海なんです。そういう原体験があったからかもしれませんが、福島の原発事故が他人事に思えなかったことも、自分を映画制作に走らせた理由の一つだと思います。
●前作の好評価を受け東京五輪までの撮影を決意
――なるほど、ご自身に関係した思いもあったのですね。ただ、プロフィールを拝見すると、東京とニューヨークを行き来する生活を送っていらっしゃると書かれてますが、福島に8年間通ってドキュメンタリーを撮ることって難しくなかったですか?実際はどの程度の関わりをもって取材されたのでしょう。
中村監督:まず、基本的な拠点は東京で、最近はほとんど日本で活動しています。現地との関わり方ですが、最初は2013年の夏に行って、その後、同年の秋から2014年の春まで頻繁に通い、ナオトさんの暮らしぶりを取材させていただきました。そして、2015年に前作を発表したんですが、モントリオール映画祭をはじめいろんな映画祭に招待されて、ナオトさんと一緒に舞台あいさつにも出たりして、だんだんと親交を深めていった感じですね。一作目が好評価をいただいたので、これは乗りかかった船だと思い、毎年春に富岡町を訪れ、帰還困難区域にある桜の名所を定点観測しながらナオトさんの暮らしぶりをカメラに収めることを決意しました。

――それが2021年の東京オリンピックを見届けるまで続けたということですね。
中村監督:そうですね。2021年、震災10年を超えて、復興五輪を掲げる東京オリンピックが終わるまでを見届けようと。
――都会育ちの中村監督にとって、最初の頃は環境も整備されておらず、取材するのも大変だったんじゃないですか?
中村監督:私が行き始めた2013年の夏には、ナオトさんの住んでいる地域が避難指示、解除準備区域みたいになっていて、決められた時間帯だけ行き来できる状態でした。別にそれ以上滞在していても誰も何も言いに来ないんですが、いわゆる許可証がなくても入れるようになっていて、電気も通っていました。ただ、上下水道はなく、お店もなく、人もいないので、Jヴィレッジ(サッカーのナショナルトレーニングセンター)がある広野町のコンビニまで行って、水や食料を買ってくるという感じで、トイレとかは湧き水で流すような状態でした。お風呂が無くても気にしない戦地カメラマンみたいな人たちはそこで泊まったりしていましたが、私は女性ということもあっていろいろ不都合もあるし、お風呂にも入りたかったので、唯一あった広野町のビジネスホテルみたいなところに泊まって通っていました。
●ナオトさんは福島のクロコダイル・ダンディー!
――実際にナオトさんにお会いした時の印象はいかがでしたか。
中村監督:最初は懐疑的でした。特に日本の大手メディアは取材には来るけれど、「まともに紹介してもらえない」という印象が強かったみたいですね。たぶん、若い記者が熱意を持って取材に来ても、結局、上司が企画を通してくれないということもあったらしいので、「私が映画にします」と言っても、「大丈夫か?こいつ」みたいな感じでしたね(笑)
――ナオトさんは海外メディアの報道通り、動物の世話が理由で残ったと?
中村監督:ナオトさんも、最初は避難所に向かったらしいのですが、なんだか窮屈で居心地が悪いということで、町に戻ることにしたんだそうです。それで、周りを見渡したらお腹を空かせた動物たちがいっぱいいたので、仕方なく世話をはじめたら出られなくなってしまったみたいで。別に動物たちのためにわざわざ残ったわけではなくて、たまたま同じ町の住人である動物たちがそこにいたから世話し始めた…正直、それがキッカケだったと本人がおっしゃっていました。

――映像を観ていると、なんとなく“自然児”という感じですね。
中村監督:撮影している間も、普通の人間のドキュメンタリーと思って撮っていなくて、なんとなく“動物”のドキュメンタリーを撮っている気分でしたね。それくらいナオトさんと動物の距離感がすごく近くて、「動物は庇護されなければいけない」とか、「世話をしなければいけない」とか、上から目線ではなくて、あくまでも同列という感じなんですよね。新たな命が生まれ、死んでいく中で、ナオトさんは変わらず動物たちに淡々と餌をやり日々を過ごしている。新たにニワトリを飼い、蜜蜂を育て始めたのも、明日を生きていくため。自然体で共存している姿をずっと観ていたら、本当の家族のように思えてきました。
――ちょっとクセのあるキャラクターがいいですよね。
中村監督:普通の人間として測るとよくわからないところがあるんですが、動物だったら別にあり得るか…みたいな(笑)。だから私は、福島の“クロコダイル・ダンディーって呼んでいました。もう野生のおじさんだから、都会の人の尺度で測れないんです。ただ、彼には彼なりの熱い思いが実は心の底にあるんですよね。
――それはどういった思いなんですか?
中村監督:ナオトさんは高校を卒業して、最初の第一、第二原発の建設に関わったそうです。その後、埼玉の方で土建屋さんを営み、かなり儲かったようですが、バブル崩壊で仕事が全て無くなり、地元に引き上げてきたそうです。だから、ずっと日本の経済に翻弄され、ひいては自分の原点でもある原発にも翻弄されたみたいな“怒り”が根底にあったと思うんですよね。「オラ、何にも悪いことしてねぇ。悪いことしたのは国だべ」――この言葉はそれを象徴しているように思えるんです。動物の殺処分命令に対しても、人間が食べるために殺されるのは受けられる。でも、無意味に殺されることは受け入れられない。人間の勝手で汚染されている動物を殺していいはずがないだろうと、彼は主張しているわけです。
――だからですかね。ナオトさんの生きざまを通して観ると、富岡市の今が素直にスーッと心の中に入ってくる。震災を扱った映画って、どうしても観る側も構えてしまうんですが、そういう邪念が全くないんですよね。
中村監督:私も福島の原発問題だからといって、説教くさい映画にしたくなかったので、ナオトさんの存在は大きかったですね。まだ何も終わっていないのに、全国で原発再稼働の動きは、粛々と進められようとしている。そんな日本の矛盾の渦中にある福島で、ナオトさんは今、動物たちとどんな思いで暮らしているのだろう…彼の生きざまを見つめながら、私たちの今を考えられたらいいなと思いました。

――富岡町で牛飼いをやってきた半谷信一さん、トシ子さんご夫婦(2017年に帰還)も強烈でしたね。
中村監督:面白いキャラクターですよね。お二人もこの状況をちょっと冷めた目で見ながら、普通に笑って生活してるんです。私はそこが凄く面白くて、逆に癒されに行ってたような気持ちになりました。
●月並みですが福島の原発事故を忘れないでほしい
――前作も含め彼らの生きざまを通して富岡町の今を観て、監督自身、何か思うところはありましたか。
中村監督:カメラが介在すると、対象者が身構えてしまって変わるって言われますが、ナオトさんも半谷さんご夫妻もそういう感覚はほとんどないんですよね。常に自然体で何も気にしていない。だから最初、この映画のデザインを考えたときに、パッと浮かんだのが、『不思議惑星キン・ザ・ザ ミーツ 人生フルーツ』みたいなイメージだったんです(笑)。無人地帯になった場所に桃源郷を作ってしまった人みたいな。正直、最初にこの町に降り立った時、人がいなくなって、自然も動物ものびのびと楽しそうに暮らしていて、「意外とここはパラダイスかもしれない」と思ったんですよ。本編の中で、水を飲んでいるポニーのヤマに、ナオトさんと半谷さんが「ここ天国だべ」と声をかけているシーンはまさに象徴的ですよね。いろんな過酷な状況があって、人も動物もサバイバルはあったわけですが、それを通り越えたらパラダイスがあった…みたいな。ここだけを切り取ると、そんな風にも観えてくるから不思議です。

――なるほど。笑いと悲しみが表裏一体であるように、どんな状況であっても小さな幸せはあるわけですよね。でも、希望は…というと、それはまた別問題のような気がします。映画は完成しましたが、これからもナオトさんたちを追い続けるんですか?
中村監督:どこまで追い続けられるかわかりませんが、もう家族みたいな感じなので、ここまで来たら、とりあえず行けるところまで行きたいですね。
――最後に読者の皆さんに伝えたいこと、訴えたいことがあれば。
中村監督:今回、この作品を宣伝していて思うのが、メディアがあまり関心を持ってくれないこと。ある知り合いのライターさんが大手メディアに取材を提案したら、「世の中はむしろ原発再稼働の方向に向かってるから、こういう話はできない」とあからさまに言われたそうです。まだ収束もしていないのに、「もう終わった話」になっていると。2015年公開の前作は結構大きく上げ取り上げてくれたんですが、風当たりの冷たさを感じています。コロナの蔓延もありましたから仕方ない部分もありますが、原発問題はまだまだ続いているので、月並みですが、福島を忘れないでほしいですね。この問題を考えると、『花はどこへ行った』という歌を思い出します。同じ過ちを繰り返してばかり、いつ私たちは学ぶのだろう…。「原発事故から10年経って、今、何を思いますか?」と、私はナオトさんと半谷さんたちに尋ねました。そして、彼らから出てきた答えに驚愕しました。この映画の中で、観客の皆さんにぜひそれを確かめていただき、考えてもらいたいと切に願っています。(取材・文:坂田正樹)
撮影・監督・編集:中村真夕

16歳で単身、ロンドンに留学。ロンドン大学を卒業後、ニューヨークに渡る。コロンビア大学大学院を卒業後、ニューヨーク大学大学院で映画を学ぶ。アメリカの永住権を持ち、今も東京とニューヨークを行き来して暮らす。2006年、高良健吾の映画デビュー作、「ハリヨの夏」で監督デビュー。釜山国際映画祭コンペティション部門に招待される。2011年、浜松の日系ブラジル人の若者たちを追った劇場用ドキュメンタリー映画「孤独なツバメたち〜デカセギの子どもに生まれて〜」を監督。2014年、ドキュメンタリー映画「ナオトひとりっきり」を監督。2015年モントリオール世界映画祭に招待され、全国公開される。
脚本協力作品としては第45回エミー賞ノミネート作品「東京裁判」 (NHK)29年度芸術祭参加作品がある。ドキュメンタリー映画「愛国者に気をつけろ!鈴木邦男」は2020年の2月にポレポレ東中野で異例の2週間連日満席記録を更新した。2022年春、黒沢あすか、神尾楓珠主演の劇映画「親密な他人」を公開。本作は第34回東京国際映画祭のNippon Cinema Now部門に正式招待される。最新作は劇映画「ワタシの中の彼女」。公式ホームページ:http://mayunakamura.com
出演:松村直登、松村代祐、半⾕信⼀、半⾕トシ⼦、富岡町の動物たち/撮影:中村真⼣、辻智彦/編集:清野英樹/監督:中村真⼣/製作・編集協⼒:⼭上徹⼆郎/製作・配給:Omphalos Pictures, Siglo/配給・宣伝協⼒:ALFAZBET/2023 年/⽇本/⽇本語/HDV/カラー/106 分