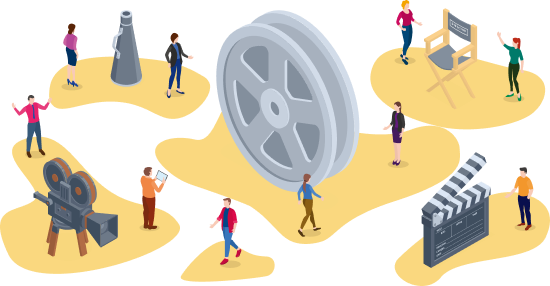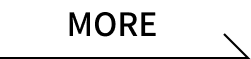「TSUTAYAコミック大賞」「このマンガがすごい!」など主要漫画賞にノミネートされ、「マンガ大賞2020」を受賞。アニメ化やYOASOBI「群青」とのコラボレーションでも話題を集め、累計発行部数は700万部を超える大ヒットを記録した山口つばさの傑作漫画を、眞栄田郷敦主演、高橋文哉、板垣李光人、桜田ひより共演で実写化した映画『ブルーピリオド』が、いよいよ8月9日(金)より公開される。これに先駆け、本作のメガホンをとった萩原健太郎監督(『東京喰種トーキョーグール』『サヨナラまでの30分』)に、人気漫画を映像表現することの楽しさ、難しさ、若手実力派を揃えた絶妙のキャスティング、そして本作に込めた熱い思いを聞いた。

<Story> 成績優秀、周りの空気を読みながらソツなく器用に生きてきた高校2年生・矢口八虎(やとら/眞栄田)。ある日、美術の授業で「私の好きな風景」という課題が出され、悩んだ末に、一番好きな「明け方の青い渋谷」を描いてみた。その時、絵を通じて初めて本当の自分をさらけ出せたような気がした八虎は、美術に興味を持ちはじめ、どんどんのめりこんでいく。そして、国内最難関の美術大学“東京藝術大学”への受験を決意する。 だが、正解のないアートという大きな壁、さらには強力なライバル達が立ちはだかり、もがき苦しむ八虎。経験も才能もない彼は、果たして「自分だけの色」で藝大合格を手にすることができるのか…。

●漫画をそのまま再現するだけなら映画化する意味がない
――この漫画原作を萩原監督が映画化することになった経緯を教えていただけますか?
萩原監督:2020年の初夏だったと思いますが、僕が監督した映画『サヨナラまでの30分』を観てくださったワーナー・ブラザースとC&Iエンタテインメントのプロデューサーさんから、「この漫画をぜひ一緒に映画化したい」とお声がけをいただいたのが最初です。ただ、ほかの映画会社さんも手を挙げていましたし、連続ドラマにしたいというテレビ局もあったんですが、最終的に僕たちが提案した企画書と演出プランを選んでいただいた、という流れです。

――萩原監督自身のお考えを知りたいのですが、漫画原作、特に熱烈なファンが多いコミックを 実写化する際、「1番大切にすること」「挑戦してみたいこと」、そして「絶対にやってはいけないこと」、この3つを教えていただけますか?
萩原監督:一番大事なことは、この原作の“何”がこれほど多くのファンの心を惹きつけているのかを見極めること。例えば、『ブルーピリオド』で言えば、藝大(東京藝術大学)受験に対するリアリティーですよね。好きという気持ちだけで立ち向かっていくことだったり、好きなことをひたむきにやり続けることだったり、それに伴う喜びだったり、痛みだったり…それぞれのキャラクターが抱えるいろんな感情をとにかく丁寧に描くことが大切なわけです。ところが、映画は概ね2時間しか尺がない。キャラクター全員の気持ちを掘り下げることは不可能ですから、どうしても取捨選択を迫られるのですが、絵に目覚めたばかりの“凡人=八虎(眞栄田)”の物語を中心に置きながら、彼に立ちはだかる“天才たち”という構図を作ることによって、グッと絞り込むことができたかなと思います。

――藝大合格に向かって必死に努力する八虎と、ユカちゃん(高橋)、世田介(板垣)ら天才たちとの“コントラスト”が明確で、キャラクターの個性や感情の動きをより際立たせていましたね。挑戦という意味でどうでしょう、何かトライされたことはありますか?
萩原監督:いかにして“映画的意味”を持たせるか、ということですかね。漫画は“絵”と“言葉”のメディア。その重要性が半々ぐらいだとしたら、映画は言葉が2、映像が8。そう考えると、映像でどう物語を伝えていくか…ただ撮るだけではなく、そこに意味を持たせないといけない。今回は、ドラマの中に「光を求める八虎が、最終的にその光を生み出していく存在になる」という軸を作って、それを映像でどう表現するかを模索しました。トンネルを抜けて光に向かって行くシーンや、光に手をかざすシーンなど、光と影を使った映像が結構印象に残ると思いますが、まさにそれは、映画だからこそできる表現だと思います。

――光の表現も素晴らしかったのですが、本作を観て感心したのが、受験生たちの“心の躍動”が映像からビンビン伝わってくるところ。美術はどちらかというと“静”の題材だと思いますが、“動”の物語として演出されているところもチャレンジングな感じがしました。
萩原監督:そうですね、絵を描くという行為がどうしたらドラマティックに見えるか、ということはすごく考えました。その中で、興味があったのは、「凡人が情熱だけで天才に勝てるのか」「藝術などの創作活動は才能がある人だけのものなのか」という問いに対する挑戦。僕も天才ではないし、周りに天才と呼ばれる人がいたら普通に嫉妬しますから、そういう特別な人たちに対して「そうじゃない!」と八虎を通して言いたかったところはありますね。だから、原作はもう少しマイルドで臆病な感じですが、映画はかなり男の子っぽく、挑戦的な作品になっているかもしれません。

――逆に、漫画原作を実写化する上で、萩原監督の中で絶対にやってはいけないことは何ですか?
萩原監督:実写化に盲目的になるあまり、漫画がこうだから同じ表現にするとか、ファンがこのシーン好きだからそのまま再現するとか…だったら「漫画でいいじゃん」ってなるわけです。 映画にする意味がない。僕はやっぱり、漫画「ブルーピリオド」のコアな部分を大切にしながら、あくまでも映画『ブルーピリオド』という独立したものを作りたかったので、心のよりどころとして撮影現場に原作を持ち込んだりもしませんでした。
――キャラクターの“ヴィジュアル”に関しても再現性は必要ないと?
萩原監督:ヴィジュアルに関しては、原作漫画をできるだけ再現しなければならないと思います。ただ、真似をするだけなら単なるコスプレになってしまうので、なぜこの髪型なのか、なぜこの衣装なのか、映画化するにあたって意味づけがきちんとされていなければならないと思います。


●ストイックな4人がキャラクターの個性を輝かせた
――映画を拝見して、これ以上のキャスティングはないと思わせるくらい、皆さん魅力的で役にフィットしていました。この4人を選んだ経緯を教えていただけますか?
萩原監督:プロデューサーの皆さんと一緒に決めさせていただいたのですが、八虎役が一番番難航しました。原作ではもう少し優男(やさおとこ)のイメージだったので、郷敦くんだと男らしすぎるかなと思ったんですが、彼自身、プロのサクソフォーン奏者を目指して藝大を受験し、不合格だった経験があり、その大変さを知っているというところから役に入れるのはアドバンテージとして強いんじゃないのかな、ということで、オファーさせていただきました。八虎役が決まってからは、いわゆる“天才たち”のキャスティングが一気に進んだ感じでしたね。高橋世田介役の李光人くん、森まる役のひよりちゃんはイメージ通りだったし、鮎川龍二ことユカちゃん役は、顔立ちが美しいだけでなく、瞳の奥にある芯の強さを感じさせる文哉くんなら、性別に関係なく“ユカちゃん”という唯一無二の存在を演じられるだろうと思って彼に託しました。

――見事にキャスティングがハマりましたね。撮影中の4人の様子はいかがでしたか?
萩原監督:全員がストイックで素晴らしかったですね。それが相互作用して、それぞれのキャラクターがより際立っていたように思います。
――できればお一人ずつ、エピソードを盛り込みながら現場での印象を教えてください。
萩原監督:郷敦くんに関しては、半年ぐらい絵画練習をしたんですが、最初の段階から飲まず食わずで6時間、ぶっ続けでやるぐらいの集中力がありました。「何か食べる?」と聞いても、「いらないです」と言って没頭している。 言葉数は少ないですが、内に秘めた情熱がすごいなと思いました。

文哉くんの場合は、ユカちゃんという役に対する覚悟というか、ストイックさがひときわすごかったですね。撮影が始まる前、「監督、どういう体形がいいですか?」と聞いてきたので、具体的にイメージを伝えたら、体重を8kgも落として、その通りの姿になって撮影に現れたんです。喋り方やしぐさも細かく調整してきたり、原作では描かれていない感情の部分も自らいろいろと提案してきたり…俳優として頼もしささえ感じました。

李光人くんは、撮影が終わったあと、「とても楽しかった!」と言っていたので、世田介役を満喫したようでした。演出していて思ったのは、彼はのびのびやった方がいい結果に繋がるタイプ。こちらが縛りつけるのではなくて、自由に演じてもらった方が、彼の人と成りの良さみたいなものが出るんじゃないかと。今回は八虎を苦しめる役回りにしたかったんですが、こちらの意図を汲み取るのもうまいので、わざわざ説明しなくても世田介役を完璧にまっとうしてくれました。

ひよりちゃんは、中学生の時に『東京喰種 トーキョーグール』で1度ご一緒しているんですが、俳優業にもすっかり慣れて、今ものすごく忙しいので、逆に緊張感を持ってもらうために、本読みに来てもらって郷敦くんと二人で合わせてもらったり、プロデューサーも参加して役について細かく打ち合わせをしたり、こちらの熱量を伝えることに力を注ぎました。その甲斐あって、時間がない中、森まるという役を自分なりに理解して演じてくれたので、持ち前の高いスキルを発揮してくれたと思います。

――それぞれ特徴があって面白いですね。ところで、絵画練習というワードが出てきましたが、これは皆さん、撮影前に結構やられたんでしょうか?
萩原監督:やりましたね。最初に座学から入ったんですよ。もう何人も藝大に送り出してる先生がいて、普通の生徒が1年かけてやるカリキュラムを半年にギュッと詰め込んで、そのあと、石膏、デッサン、油絵(または日本画)という流れを一通り経験してもらいました。藝大受験のために必要なステップを疑似体験できたことは、役づくりにおいてとても有意義なことだったなと思っています。



――なるほど、そこまでやり切ったからこそ、あれだけのリアリティーが生まれたのですね。最後にまとめのメッセージをいただきたいのですが、インタビューの最初の方で、「漫画原作のコアな部分を大切にしながら、あくまでも映画『ブルーピリオド』という独立した作品を作りたい」とおっしゃっていましたが、それを踏まえながら、本作を製作した意義を教えていただけますか?
萩原監督:原作はこれからも続いていくと思いますが、 映画はここで完結するので、全然違うものなんですよね。だったら、「この映画の役割ってなんだろう」って考えた時に、 例えば情熱が枯れてしまったり、モチベーションが下がってしまったり、気持ちが落ちてしまったり…何らかの理由で苦しんでいる時にこの作品を見直すことで、 再び気持ちがブーストするというか、情熱を取り戻すというか、皆さんの心に一生寄り添っていける映画になればいいなと思っています。宣伝部が考えてくれた「情熱は、武器だ。」というキャッチコピーがありますが、まさにこれですよ!きっと自分も、何かに疲れ果てた時、この映画を見返して、情熱をチャージすると思います。
(取材・文・写真:坂田正樹)

<Staff & Cast> 出演:眞栄田郷敦、高橋文哉、板垣李光人、桜田ひより、中島セナ、秋谷郁甫、兵頭功海、三浦誠己、やす(ずん)、石田ひかり、江口のりこ、薬師丸ひろ子/原作:山口つばさ『ブルーピリオド』(講談社「月刊アフタヌーン」連載)/監督:萩原健太郎/脚本:吉田玲子/音楽:小島裕規 “Yaffle” /主題歌:WurtS「NOISE」( EMI Records / W’s Project)/製作:映画「ブルーピリオド」製作委員会/制作プロダクション:C&Iエンタテインメント/配給:ワーナー・ブラザース映画/公式サイト:blueperiod-movie.jp

©山口つばさ/講談社 ©2024 映画「ブルーピリオド」製作委員会