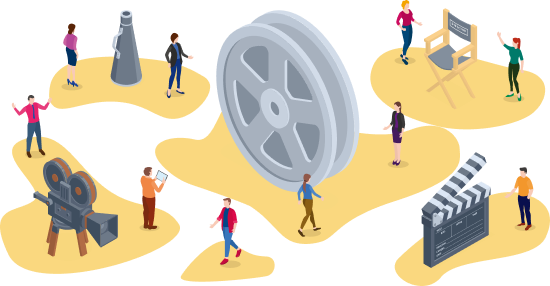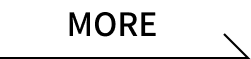恋人からプロポーズを受けた翌日に、忽然と姿を消した市子。やがて、彼女と関わりがあった人々の証言から、市子の底知れない人物像と、切なくも衝撃的な真実が次々と浮かび上がってくる。名前を変え、年齢を偽り、社会から逃れるように生きてきた市子。彼女はなぜ、そんな日陰のような人生を歩まなければならなかったのか…。原作は、戸田彬弘が主宰する劇団チーズ theater 旗揚げ公演作品。サンモールスタジオ選定賞 2015最優秀脚本賞を受賞した舞台劇を戸田自らがメガホンをとり、映画『市子』が完成した。

痛ましいほどの過酷な家庭環境で育ちながらも、「生きること」を諦めなかった主人公・川辺市子を演じるのは、『楽園』『湯を沸かすほどの愛』などの杉咲花。抗えない境遇に翻弄された市子の壮絶な半生を、凄まじい熱量で体現してみせた。ただ、とてつもないエネルギーをスクリーンに焼き付けながら、市子を生み出した戸田監督も、市子を演じた杉咲も、「彼女のことがわからない」と口を揃えて語る。果たしてその真意とは?市子を追いかけ続けた2人にその舞台裏を聞いた。
●名作『羅生門』の構造をヒントに映画化を実現
――戸田監督にお聞きします。脚本作りで大変苦心されたそうですね。黒澤明監督の『羅生門』(原作:芥川龍之介/1950)の構造を採り入れたことで映画化が可能になったとお聞きしましたが、そうなると、逆に舞台ではどのような構成だったのか気になります。
戸田監督:舞台の市子は、どちらかというとマネキン的(抽象化)な扱いというか、市子の周りの人たちが彼女に対して「こんなことがあった」とか、「こんな一面があった」とか、いろいろ証言していくんですが、舞台上にさらにステージみたいなものを作って、そこで市子がその証言を演じていく、というスタイルで描きました。構成的には、「市子はそこにいない」ものとして考察していくという感じですね。
――それをそのまま映画化するとなると、確かに難しいですね。
戸田監督:舞台では、市子が市子自身を演じているけれど、それ自体、今起こっていることではなく、抽象化されているものであって、演劇はそういう描き方に特化しているというか、お客様はそれを勝手に咀嚼していくものなので成立するんですね。ところが映画の場合は、カメラで市子というキャラクターを映していくと、そこに実存しているようなニュアンスでどうしても映ってしまうんです。SFとかファンタジーとかであればやり方があると思うんですが、リアリティーのあるドラマを撮りたい場合、市子を映していくと、やはりそれが真実になってしまうので、映画化するのはかなり難しいなと思いました。

――それをクリアしてくれたのが『羅生門』の構造だったわけですね。
戸田監督:大きなヒントになりましたね。『羅生門』は登場人物それぞれの証言によって出来事が藪の中に入っていく構造になっていますが、その手法に倣(なら)えば映画化できるんじゃないかと。各章ごとに市子と関わりのあった人物を主人公にして、それぞれの視点から市子を見つめていく構成で脚本を再構築すればいけるかもしれないと思い、共同脚本の上村(奈帆)さんと試行錯誤しながらなんとか道を拓きました。
――杉咲さんにお聞きします。脚本を読まれた時、うまく言葉にできない“シンパシー”を感じたそうですが、先が見えない怖さはありませんでしたか?躊躇することなく「挑みたい」と背中を押した一番の要因は何だったのでしょう。
杉咲:本を初めて読んだ時に、涙が出たことは事実なのですが、 “シンパシー”という言葉が適切だったのかどうか、自分の中で改めて見つめ直したりもしていて…。というのも、それが感動や同情から来るものではなく、何か正体のわからない、これまで味わったことのない感覚に襲われたんですよね。

――正体のわからない感覚…まさに市子というキャラクターと被りますよね。
杉咲:市子が穏やかな暮らしを追い求めるのは、幸福であることを知っているからなのではないかと思ったんです。その感覚をどういった時に味わって、どういうものとして市子の心の中に残っていくのか…。それが知りたくて「演じたい」と感じたのではないかなって。
――かつてない難役だったと思いますが、演じる怖さみたいなものはなかったですか?
杉咲:演じている時なのか、現場での人との関わりを通してなのか、まだ行ったことのない境地に辿り着いてしまうような…そんな予感があって。そこで何が起こるのか、眼を塞ぐ指の隙間からのぞいてしまいたいような感覚でした。
――実際に市子を演じてみて、その予感は当たりましたか?
杉咲:そう思います。

●『おちょやん』で磨いた関西弁が役に生きた
――戸田監督が杉咲さんを市子役にキャスティングした経緯についてお聞きしたいのですが、俳優としての杉咲さん自身の魅力、そして市子役にふさわしいと思った理由を教えていただけますか?
戸田監督:脚本を書いている途中は、あまりキャスティングのことは考えず、本を固めていくことに集中していましたが、ほぼカタチが見えてきた時、「市子役を誰に預けようか」ということを意識し始めました。原作では市子が東大阪出身で関西弁をしゃべるんですが、映画でもリアリティーのある作品に仕上げたいという思いがあったので、そこの設定は変えずに関西出身の役者リストを作ったんです。ただ、市子としてしっくりくる方がいなかった。そんな時に、連続テレビ小説『おちょやん』(NHK)で、東京出身の杉咲さんが完璧な関西弁でヒロインを演じているのを思い出して、「ネイティブじゃなくてもいけるかもしれない」と思ったのが最初ですね。もちろん、杉咲さんの映画やドラマはずっと注目して観ていましたが、『楽園』(監督:瀬々敬久/2019)という映画を観た時に、杉咲さんの“目”から物凄いエネルギーと、ある種の怖さみたいなものを感じて。『おちょやん』のような陽のヒロインを素敵に演じているあの杉咲さんが急に引力のある目をされているのが素晴らしく、この振り幅こそ市子を演じるにふさわしいと思い、プロデューサーにお願いして手紙を送らせていただきました。
――戸田監督から直筆の手紙をいただいた時、どんな気持ちでしたか?
杉咲:お手紙を直筆で届けていただくことって、「伝えたい」という気持ちが一歩進んだ状態だと思うんです。さらにその内容が「監督人生の分岐点になる作品だと思っています」という、とても熱を帯びたもので、それほど大切な作品に自分を求めてくださったことが何よりも嬉しかったです。

――そもそもの話になりますが、リアリティーを語る上で関西弁にこだわる理由はなんだったのでしょう。
戸田監督:日本の現代とリンクしているというか、どこかに市子のような女性がいるんじゃないかと。フィクションではなくて、ノンフィクションとしてダイレクトにお客様に伝わらないといけない、という思いで、市子を東大阪出身にしました。そうなると、リアルな関西弁のイントネーションじゃないと、どこかにフィクションのような空気が生まれてしまうので、まずそこを避けたいというのが言葉にこだわった理由です。そもそも標準語だと特定性を失ってしまうので。
――なるほど、だから関西出身の俳優さんを探していたんですね。ところが、その縛りを杉咲さんが超えてきた。『おちょやん』の関西弁、違和感のかけらもなかったですが、初めての経験だったんですか?
杉咲:『おちょやん』で初めて教わりました。方言指導の先生が1年ほどかけて、付きっきりで指導してくださったので、本当にそのおかげです。
――関西弁が体に染みついている感じですか?
杉咲:特に『おちょやん』では10ヶ月以上かけてずっと話していたので、関西弁が聞こえてくると、何というか、郷愁のようなものを感じてしまいます。

●固まっていない姿を撮ることが『市子』の生命線
――基本的にワンテイク1発勝負で撮影に挑んだそうですが、その狙いは何だったのでしょう。
戸田監督:テーマであるリアリティーを追求するために、カメラワークも含めて、ある種ドキュメンタリーっぽく撮りたいという狙いがあったので、整いすぎた市子が映ることを避けたかった、というのが大きな理由です。お芝居って、何度も繰り返すと、鮮度も無くなるし、自分の中で見せ方をコントロールされる方もいるので、そうなる前の固まっていない姿を映した方がいいんじゃないかなっていうのもありました。
――演者である杉咲さん自身は、相当役にのめり込んでいたと思いますが、撮影期間中、どのような心境で過ごしていたのでしょう。ずっと市子を生きている、あるいは追いかけていると、心が苦しくなりそうですが…
杉咲:撮影してない時は、フラットな気持ちでいることを意識していました。以前は、プライベートの時間と演じている時間の境目がわからなくなってしまう感覚に陥っていた時期もあったのですが、それが必ずしも役にいい影響を与えるとは限らないという考えに変わってきて。役としての心情でプライベートな時間を過ごすことによって、役のことをわかったつもりになってしまう危うさを感じ始めたんです。

――なるほど、経験を積み重ねるうちに変わってきたんですね。
杉咲:今回、市子という役を演じてみて、演じ手としての“欲”から解放されるというか、そういった邪念が剥がれ落ちて、その時目の前で起きていることに体が反応してしまうだけの時間を過ごせた瞬間があったんです。それは自分にとって初めての経験でした。「これが役を生きるということなのかな?」と錯覚した瞬間もあったのですが、また別の日になると、新しい壁に直面して市子の感覚がわからなくなってしまう。「こんな状態でカメラの前に立ってしまっていいのだろうか」と不安に苛まれる瞬間もあって、その繰り返しのような日々だったんです。
――役に憑依するどころか、市子をどこまでも追いかける…そんな感覚なんでしょうか?
杉咲:そうですね。私にとっては、どこまで行っても他者は他者であるんだということが腑に落ちるような時間でした。役のことをわかるなんて不可能に近いのではないかなって。だからこそ、憑依するとか、役に入り込むということは、自分にとってはとんでもないといいますか…。想像して、想像して、限りなく市子の心情に接近することに力を注ぎたいと思いました。今は、それが演じるということなのかなと思っています。

――何かこう“生もの”のような感覚がありました。触ると壊れてしまいそうな…
杉咲:たぶん、何テイクも重ねていたら、また違った印象になっていたのではないかと思います。1度OKをもらったものを基準と捉えて、お芝居が完成されていってしまうといいますか。戸田組での撮影において、そこで起こったことに対して純粋に受け止める時間を大事にしていただけたということは、本当にありがたい環境だったなと思います。戸田監督には感謝の気持ちでいっぱいです。
●「市子のことがわからない…」これこそがテーマ
――戸田監督自身がキャラクターを生み出し、そして、杉咲花という役者を通して映画を世に送り出した今、市子にどんな感情を抱いていますか?
戸田監督:自分が原作で書いたキャラクターですが、もう触れられないところにいる感じはありますね。杉咲さんに演じてもらったということもありますが、ご覧になる皆さんにいろんなことを考えさせるキャラクターなんだろうなと思います。原作を書いていた時も、「この子がわからない」と思いながら書いていたんですが、それを“わかったつもり”で書くしかなくて…。完成した映画を観た時も、なんとなくわかった気になりそうなんですが、最終的に「やっぱり市子のことがわからない」と思ってしまったんですね。つまり、それはある意味、「わかった気にならない」というこの作品のテーマでもあるというか…。それだけに凄いエネルギーを持ったキャラクターだったんだなと今は思っています。

――愛おしいけれど、壊れてしまいそうで近づけない…。だから、映画を観終わったあと、杉咲さんがパンのCMで元気そうに食べている映像を観た時は、なんだかホッとしたというか(笑)。完全に市子と杉咲さんを混同している自分がいました。
杉咲:ありがとうございます(笑)。「モデルになった人がいるんですか?」と聞かれる機会が多いのですが、そんなふうに市子のことを実在する人物として受け止めていただけることが嬉しいです。
〈Staff&Cast〉 出演:杉咲 花、若葉竜也、森永悠希、倉 悠貴、中田青渚、石川瑠華、大浦千佳、渡辺大知、宇野祥平、中村ゆり/監督:戸田彬弘/原作:戯曲「川辺市子のために」(戸田彬弘) /脚本:上村奈帆、戸田彬弘/音楽:茂野雅道/エグゼクティブプロデューサー:小西啓介、King-Guu、大和田廣樹、小池唯一/プロデューサー:亀山暢央/撮影:春木康輔/照明:大久保礼司/録音・整音:吉方淳二/美術:塩川節子/衣装:渡辺彩乃/ヘアメイク:七絵/編集:戸田彬弘/キャスティング:おおずさわこ/助監督:平波 亘/ラインプロデューサー:深澤 知/制作担当:濱本敏治/スチール:柴崎まどか/文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会/制作:basil/制作協力:チーズ film/製作幹事・配給:ハピネットファントム・スタジオ/2023 年/日本/カラー/シネマスコープ/5.1ch/126 分/映倫 G /公式サイト:https://happinet-phantom.com/ichiko-movie/