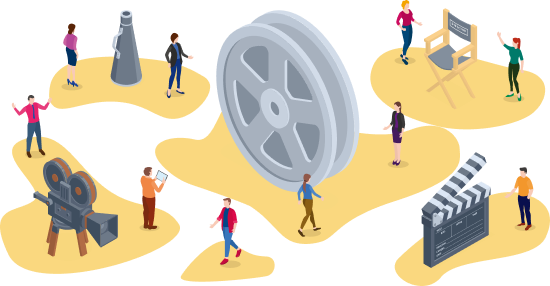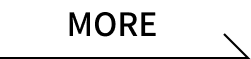宮川氷魚、南沙良、内田理央、福地桃子ら多数のスター俳優が所属する芸能プロダクション・レプロエンタテインメント(以下、レプロ)が企画した「感動シネマアワード」グランプリ6作品目となる映画『夢の中』が5月10日(金)よりアップリンク吉祥寺ほか全国順次公開される。主人公は果たしてこの世に生存する人間なのか?つかみどころのない難役に挑んだレプロ所属俳優の山﨑果倫とプロデューサーの菊地陽介に、本作制作の舞台裏、さらには「スターをつくる」という命題のもと、俳優育成に力を注ぐレプロの現在について話を聞いた。

「感動シネマアワード」とは、多種多様な“感動”を肯定し、観客の“心を揺さぶる”企画を全国から募集し、レプロ出資のもと製作する映画コンペティション企画。これまで、『階段の先には踊り場がある』(監督・木村聡志、主演・植田雅) 、『あの娘は知らない』(監督・井樫彩、主演・福地桃子)、『世界は僕らに気づかない』(監督・飯塚花笑、主演・堀家一希) 、『はざまに生きる、春』(監督・葛里華、主演・宮沢氷魚)、『炎上する君』(監督・ふくだももこ、主演・うらじぬの)が製作され、本作が同コンペティションの最終作品となる。
<Synopsis> 本作は、中学生の性の違和感と自己理解の揺らぎを描いた『蝸牛』でMOOSIC LAB 2019短編部 門グランプリほか四冠を達成した新鋭・都楳勝(つうめ・まさる)監督最新作。『隣の男はよく食べる』(23/テレビ東京)、『輝け星くず』(主演/公開中)ほか近年出演作ごとに評価を高める山﨑果倫が主演を務める。そのほか、監督作『君に幸あれよ』(23)ほか映像作家としても注目を集める櫻井圭佑、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(22/NHK)や連続テレビ小説『らんまん』(23/NHK)などの山谷花純、大河ドラマ『光る君へ』(24/NHK)の玉置玲央ら実力派が集結。




<Story> 「俺のこと、ここで匿ってくれない?」血まみれで息を切らす男・ショウ(櫻井)に声をかけられたタエコ(山﨑)。生気がなく虚ろな瞳の彼女は、部屋に入る彼に「私の最期、綺麗に撮ってください」とお願いする。何から逃れてきたのか。その願いは本当に望んでいるものなのか。二人は時間を共有するうちに、夢とも現実ともつかない、お互いの感情と記憶が交ざり合う奇異な世界に引き込まれていく。
山﨑果倫(主演)×菊地陽介(企画・プロデュース)インタビュー
◉どんな映画になる?予測不可能なワクワク感
――まず、菊地さんにお伺いします。前回、ご取材させていただいた『階段の先には踊り場がある』とは毛色の違うアーティスティックな作品でした。最初、選出されたときの脚本からかなり変わったともお聞きしていますが…。
菊地:そうですね。最初の脚本では、物語に対する具体的な描写があったのですが、撮影の段階で都楳監督の作家性というか、編集も含めた演出が入ることによってどんどん変化していきました。映画として立体化させていく中で、監督自身が求めていた作品の輪郭が生まれていった感じはありましたね。
――ほぼ最初の脚本通りに作り上げた『階段の先には踊り場がある』とは制作スタイルもまさに真逆ですね。
菊地:『階段の先には踊り場がある』は、よく「アドリブ合戦がすごい」と言われるんですが、実は最初の脚本通りに忠実に作られているんです。そこが面白いところなんですが、今回は、ベースは変わっていないものの、原形があまり感じられないくらい初稿から脚本が変更されているので、確かにその逆と言えるかもしれません。ただ、本作に関しては、才能あふれる都楳監督が、山﨑さんを主役に一体どういう演出で、どういう映画を撮るのか、そこに一番興味があったし、完成した作品を観てみたいという思いが強かったのだと思います。

――山﨑さんにお聞きします。本作は、そもそも山﨑さんに向けた企画ですが、このお話を聞いたとき、率直にどんな感想をお持ちになりましたか?
山﨑:都楳監督の作品が大好きだったので、正直驚きました。というのも、都楳監督は『蝸牛』という作品で「MOOSIC LAB 2019」短編部門グランプリほか4冠を達成しているんですが、上映期間中に私も同作を観て、すごくいいなと思って、都楳監督を出待ちして(笑)熱い思いを伝えたんです。どうやらその熱量が記憶に残っていたらしく、今回、私に当てて脚本を書いてくださったそうです。
――思いを伝えた甲斐がありましたね。送られてきた脚本を読んでいかがでしたか?
山﨑:私が演じるというのをまず切り離して…都楳監督なら絶対に観たことのない映画になるなと思いました。脚本自体は今とはぜんぜん違っていたんですが、『蝸牛』でも感じた「新しいけれど、どこか懐かしい」みたいなちょっと変わったノスタルジーが私の感覚の中にあったので、きっと都楳監督の演出に何か不思議な「魔法」があるんだろうなと思ってワクワクしていました。

――脚本がどんどん変わっていくことに抵抗はなかったですか?
山﨑:最初の脚本は、人間同士の濃密なお話で、それを都楳監督が調理したらどんな感じになるんだろうと期待していたんですが、なぜか人間同士のお話がどんどん魂同士のお話にまで抽象化されていったので、まったく予測できなくなったというか…。ただ、その変化していく制作過程を隣で見ることができて、貴重な経験をさせてもらったなと思っています。
◉「観客を信じよう」のひと言で不安が期待に
――待ちに待った完成作品、ご覧になっていかがでしたか?
山﨑:思った通り、観たこともない映画になっていました。脚本も、幻想、現実、夢が混ざったようなものだったので、完成するまで何も想像できてなかったんですよ。撮影も自分が出てるシーンしかほとんど知らなかったし、ショウ(櫻井)とアヤ(山谷)のシーンだったり、情景のシーンだったり、全く観ることができなかったから、完成作品を観たときは、その美しさにうっとりしました。ただ、この作品に出ているにもかかわらず、1回観ただけでは理解が難しくて、2回目で腑に落ちる部分がたくさん出てくるというか…客観的にこの作品を観ると、正直、そういう感想になりますね。

菊地:プロデューサーという立場からすると、編集の状態から観てきて、完パケだけでも10回ぐらいは観ているので、当然、わからないっていうことはないんですが、振り返ってみると、「音」に相当こだわっていたところが印象深いですね。オフラインの状態で映像を観ると、少しぼんやりしているんですが、音楽を含めた「音」がハマってくると、映画としてしっかり立ち上がってくる。当然、俳優陣の芝居の良さとか、映像も凝っていますし、それらが最終的に全て組み合わさると、かなり立体的で解像度が高い映画になっているなというのが最初の印象です。ただ、6作品の中で最終形が一番見えにくかったのは否めません(笑)。他の作品は編集しているところから何となくわかってくるものですが、1本の作品として立ち上がってくるのが最後の音が完成した段階だったので、そういった意味では、予想通り、ワクワクさせてくれましたね。

山﨑:そういえば、私、撮影中に不安になってきて、菊地さんに聞いちゃったんですよ。「この映画、お客様に伝わりますかね?」って。それこそ完成が全く想像つかない状態で撮っていたので、どうなるんだろうと。そうしたら、「案外、大丈夫だよ。これくらいだったら絶対に伝わるから、観客の皆さんをもう少し信用しようよ」と言われたんです。「私より何倍も映画を観ていて、この映画の全体像も把握している菊地さんがそうおっしゃるんなら間違いない!」と思ったら、急に楽観的になったのを思い出しました。
――脚本が大幅に変わり、先が見えない撮影が続けば、誰だって心配になりますよね。監督やプロデューサーを信じてやり切るしかないと思いますが、この役を演じるにあたって、どういう心持ちで、タエコという役に臨んでいたのでしょう。
山﨑:私自身はすごく感受性豊かな人間で、涙もろいし、すぐ笑うんですね。だから、タエコになるために、感受性のセンサーをオフにする練習をたくさんしました。ちょっと油断するとリアクションしてしまうので、感情を「ゼロ」にして、動作も「小さく、ゆっくり」を常に心がけました。ただ、唯一タエコの本音がこぼれ落ちる微かな「ため息」があるんですが、その発声はすごく大切にしましたね。でないと、タエコは本当に100%オフのままで終わっちゃうから。

――そもそも、タエコって誰?何者?っていう素朴な疑問がありますよね。
山﨑:そうなんです。最初は、「彼女は生きてるの?」「存在してるの?」「ちゃんと息してる?」とか、いろいろ思いをめぐらせましたが、正直、演じているうちにお化けだろうが、魂だろうが、人間だろうが、誰かの心を投影した存在だろうが、なんでもいいと思ったんです。そういうことを重要視しているわけではなく、もっと研ぎ澄まされた概念みたいなところに行き着いたので、逆に「邪魔だな」と思って取り除いたらすごく演じやすくなりました。都楳監督自身も答えを持っていなさそうだったので、これはもう観客に委ねていいんだと思いました。
――プロデューサーである菊地さんの目に山﨑さんの演技はどう映ったのでしょう?
菊地:捉えどころのない役というか、かなり難しかったと思います。タエコだけでなく、ショウ(櫻井)と、その恋人アヤ(山谷)も、どこを足掛かりにすればよいか難しい役どころなのですが、二人は玉置玲央さん演じるカメラマン藤沢との関係の中で、現実との接着点が生まれます。しかし、タエコだけは地に足ついてない、現実から遊離しているキャラクターだっただけに、これは苦労するだろうなと思っていたんですが、都楳監督と密に話し合いながら少しずつ作り上げていく山﨑さんの姿勢は、純粋に素晴らしかったです。完成作品を観て、よくぞここまでやってくれたという気持ちでいっぱいですね、本当に感謝しています。
山﨑:ありがとうございます!菊地さんからそんなお言葉をいただけるなんて、ホッとしますね…嬉しいです。

――フィジカル的に大変なところはなかったですか?体を張るシーンも結構あったと思いますが。
山﨑:これは監督に言われたわけではないのですが、私の中のタエコ像は、肉づきがよくなくて骨っぽい体のイメージがあったので、半年かけて体重を6キロ落としました。儚いキャラクターにしたかったので、肌の露出が多い衣装の時は、「あばら骨がちゃんと出ているか?」というところは意識していましたね。あとは、これ、大変っていうのかな…タエコが飼っているトカゲにコオロギを(エサとして)与えて、食べるところを、虚無な目で見つめなければいけないシーンがあったんですが、私、とにかく虫が苦手で、何度撮っても「ハッ!」みたいな声が本能的に出ちゃうんですよね(笑)。このシーンは本当に大変でした。

◉私を「見ていてくれる」という心強さと安心感
――前回、「感動シネマアワード」について菊地さんにお話をお伺いした時、「スターをつくる」という命題のもと、「俳優育成に力を注ぎたい」とおっしゃっていましたが、最終作となる6作目が完成した今、その方向性の熟度というか、順調に進んでいる感じでしょうか?
菊地:そうですね。以前は映画やドラマを作るという機能は会社に存在しなかったんですが、この6作品を完成させたおかげで、「次はこんな作品をやりましょう」とか「もう少し規模の大きい作品にトライしましょう」とか、仕事の選択肢は増えました。ただ、大方針は全く変わっていません。会社として、映画やドラマの制作は単体のビジネスとして積極的にやりつつ、最終的には「スターをどうつくっていくか」というところに我々の仕事は全て向かっているので、ブレはありません。



――山﨑さんは、俳優として会社の方針といいますか、こういう取り組みについてどう思いますか?実際に『夢の中』という作品の主演に抜擢されたわけですが。
山﨑:私自身、これまで素直にまっすぐ活動してきた、というところだけは自信がありました。ただ、正直、素直すぎてもこの世界ではやっていけないのかな?という不安も同時にあったんです。だから、このお話をいただいた時は、「私のことを見てくださってる人がいる」ということが、とにかく嬉しくて…。「私のやり方で間違っていなかったんだ」と初めて実感できて、すごく報われた気持ちになりましたし、これからも活動を続けていく勇気もいただきました。外部からオファーをいただいたり、オーディションに受かったり、これまでも嬉しいことはたくさんありましたが、一番近い存在の会社が味方でいてくれる…これはすごく心強いことですし、安心感にもつながります。そこはもう感謝しかありません。
(取材・文・写真:坂田正樹)


<Staff&Cast> 出演:山﨑果倫、櫻井圭佑、アベラヒデノブ、金海用龍、森崎みのり、玉置玲央、山谷花純/脚本・監督:都楳勝/音楽:若狭真司/撮影:上野陸生/照明:佐藤仁/録音:五十嵐猛吏/美術監督:相馬直樹/衣装:中島エリカ/ヘアメイク:藤原玲子/装飾:桑田真志/水中撮影:河瀬経樹/特機:後藤泰親/編集:岸川雄大/助監督:國領正行/制作担当:三谷奏/VFXスーパーバイザー:大見康裕/タイトル:田中佑佳/スチール:持田薫、北圃莉奈子、福田啓道/企画・プロデュース:菊地陽介/宣伝デザイン:鴨川枝理『夢の中』/2023年/日本/65分/カラー/ステレオ/企画・製作・制作プロダクション・配給:レプロエンタテインメント/配給協力:インターフィルム/公式サイト:https://yumeno.lespros.co.j

©「夢の中」製作委員会