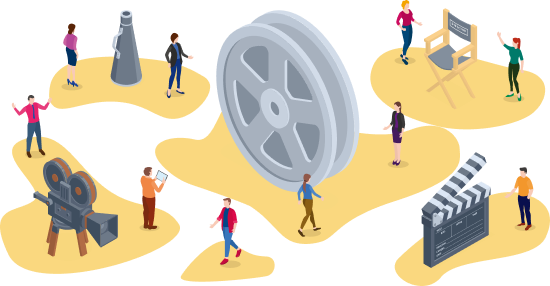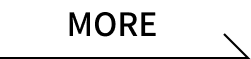真木よう子、宮川氷魚、南沙良ら多数のスター俳優が所属する芸能プロダクション・レプロエンタテインメント(以下、レプロ)が新たに企画した「感動シネマアワード」は、心温まる・圧倒される・鼓舞されるなど、さまざまなニュアンスを持つ“感動”を肯定し、 観客の心を揺さぶる作品を全国から募るという独自の映画コンペティション。
500を超える応募の中から6作品が選出され、同社出資のもと、個性溢れる作品が製作された。その第一弾を飾ったのが映画『階段の先には踊り場がある』(池袋シネマ・ロサで公開中)。劇場経営、ワークショップ、コンペティション、そして映画製作と、芸能プロダクションの枠を超えた積極的な活動を展開するレプロが目指すものとは?今回プロデューサーを務めた菊地陽介氏に話を聞いた。

作品概要:映画『階段の先には踊り場がある』は、2018年、初長編映画『恋愛依存症の女』で劇場デビューを果たし、同年池袋シネマ・ロサのレイトショー動員記録を樹立した木村聡志が脚本・監督を務めたヒューマン・コメディ。レプロ所属の新人女優・植田雅(うえだみやび)を主演に抜擢し、大学生の初々しい恋愛と、常に円満とはいかない人間関係の難しさ、そして夢に向かう希望と挫折をクスっと笑えるユーモアを交えて活写する。クセ強めの登場人物たちによるリズミカルな会話やドラマティックな回想シーンなど、木村監督ならではの世界観は病みつきになること必至!
10年以上前から俳優の育成を強化
――マネジメント以外に、劇場経営、ワークショップ、映画製作など幅広く活動を展開されていますが、レプロさんの現時点でのスタンスを教えていただけますか?
菊地:10年以上前から、芸能プロダクションとして危機感を持っていました。私たちには、社として “スターをつくる”という至上命題があるのですが、「じゃあ、そのためにこれから必要なことは何か」を考えた時に、俳優の基礎体力である演技力をこれまで以上にしっかりと磨き、育成することが必要だろうと。
――基礎をしっかり磨いても、なかなかチャンスが回って来ない場合もありますよね。
菊地:そうなんですよね。だから会社としては、ただ育成するだけでなく、そうやって毎日努力している俳優たちが表に出られるような場所を準備することが、大事なことかなと思っています。特にキャリア初期の若い俳優は、最初の仕事を取るまでがかなり難しいというか、実績や知名度がないとなかなか仕事にブッキングされません。ただ、一度その壁を突破すれば、一気にいろんなお仕事をいただいたりするので、やっぱり最初の一歩がかなり重要になってくるんです。

――2017年には浅草九劇を開業されましたが、やはり若い才能にチャンスを与えるという意味合いが大きかったのでしょうか?
菊地:まさに、それを具現化したのが浅草九劇です。「なかなかチャンスが巡ってこない…だったら自分たちで作ればいいんじゃないか」という発想です。基礎を学び、現場を通してさらに演技を磨き、切磋琢磨しながら次のステップを目指していくわけですが、“スターをつくる”という意味で、「次は何をやるべきか」を考え、エンタテインメントの王様は “映画”かなと。そういう流れで「感動シネマアワード」というコンペティションに辿り着きました。
――「感動シネマアワード」の仕組みを教えていただけますか?
菊地:若い俳優は実績や知名度がないと、なかなか仕事がもらえない現状があるので、彼ら彼女らの名刺代わりになるような作品を作ろうというのが根本にあって、今回6人の俳優をそれぞれ主演にした映画の企画で募集を行いました。『階段の先には踊り場がある』では、植田雅が主演を務めていますが、そのほか宮沢氷魚や福地桃子などが主演した作品も待機しており、順次劇場公開を目指していくという感じです。つまり、主演俳優ごとに作品を選考しているので、グランプリ受賞作は6作品あるということになります。
新人俳優が存在感を放つ演出が秀逸
――完成作品を観て、どんな印象を持ちましたか?
菊地:とてもいい作品になりました。主演の植田に関しては、演技経験が少なかったので不安ではありましたが、木村監督にうまく演出していただきつつ、また、共演してくださったキャストの素晴らしい演技に囲まれ、主演として存在感を出せたんじゃないかなと思います。映画的には、木村さんの作家性みたいなものをあまり薄めず、ただ尖りもしすぎず、ちょうどいい塩梅に落ち着いた感じですね。これが自主映画ではないということをご理解いただいたので、自分の個性や匂いを消さずに、どうやって広く届けるのか、どうやって遠くに飛ばして行くかをすごく考えてくださったように思いますね。


――会話のキャッチボールがまるでウディ・アレンの映画を観ているようで面白かったですね。たまに暴投があってイラっとしたりもしましたが…(笑)
菊地:誤解されやすいんですが、セリフはほぼ台本通りで、「まあ」とか「うん」とかまで脚本通りだったりするんですよね。撮影の時は、会話の終わりから多少アドリブで演技をしてもらったシーンもありますが、その部分は編集でほとんど落とされていました。一か所だけ残した部分はありましたが、他のシーンに関しては映画にとってあまり必要がないという判断になりました。それだけ緻密に計算された脚本だったと言えるかもしれません。
芸能プロダクションが抱える現状と未来
――最後に、芸能プロダクションの現状と未来展望についてお聞きしたいのですが?
菊地:旧来の芸能プロダクションが持っていた優位性みたいなのが、これからどんどん崩れていくと思います。自分でブランディングをしたり、自分で仕事をブッキングしたり、一人で何でも対応できる人は、芸能プロダクションを必要としない場面が多くなりました。そんな時代の流れの中で、芸能プロダクションとして何が提供できるのか。私たちが俳優さんと契約を結ぶにあたり、お互いに何を提供して、どこにメリットを感じるのか、というところが一番大事で、お互いに何もメリットを感じないのであれば、当然契約する意味がありません。お互いの利益がマッチするから「一緒にやりましょう」というのがもはや当たり前の関係性だと思います。だからこそ芸能プロダクションサイドも今までと同じ方法論ではダメだという反省が必要で、そこに危機感を持って新しいことに挑戦した結果が、今の活動に繋がっていると思います。
――そういった時代の流れも含めて、今、描いている未来の展望は?
時代の変化とともに様々な事業を始めていますが、最終ゴールは“スターをつくる”というその一点。私たちがやろうとしていることの大きな目標は全く変わっておらず、そこに尽きます。今回も映画の企画コンペティションと製作ではありますが、結局は俳優や監督などの若い才能を色々な方に知ってもらうため、彼ら彼女らが経験を積んでレベルアップするための企画です。これからも、いろんな動きをして行くと思いますが、最終的には“スターをつくる”というところに集約されると思います。それがレプロエンタテインメントの命題であり、これから生き残っていくための最大のミッションだと思っています。
◉菊地陽介/プロフィール:1989年生まれ、栃木県出身。東京大学農学部卒業。レプロエンタテインメントで映画、演劇、イベントなどのプロデュースを手掛ける。
取材・文:坂田正樹 撮影:松井証弘
©LesPros entertainment ©Soichiro Suizu