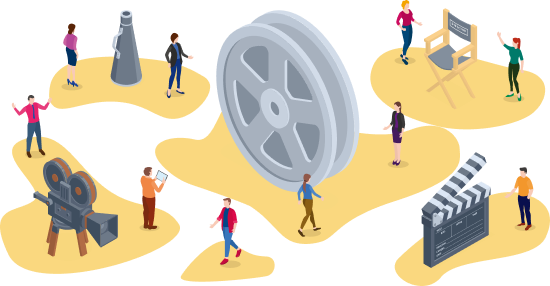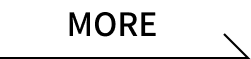「傷だらけの天使」(萩原健一&水谷豊)、「探偵物語」(松田優作)、「あぶない刑事」(舘ひろし&柴田恭兵)、さらには『私立探偵 濱マイク』シリーズ(永瀬正敏)など…思えば、1970年代~80年代は、個性溢れる俳優たちがワクワクするようなヒーロー、あるいはアウトローをイキイキと演じ、映画やドラマで所狭しと大暴れしていた。ところが近年、社会情勢やコンプライアンス、コロナによるパンデミックなども相まって、物語におけるテーマ性に重きを置く傾向が強くなり、右を見ても左を見ても真面目だらけ、いつの間にかキャラクターが際立つ破天荒な作品が鳴りを潜めていった。
そんな渇いた日本映画に風穴を開ける暑苦しいほどに痛快なハードボイルド作品が注目を集めている。現在、絶賛公開中の映画『終末の探偵』だ。ヤクザからトランスジェンダーまでどんな役でも見事に演じ切る名優・北村有起哉が、煙草プカプカ酒浸り、ギャンブル好きで借金まみれ、危険な事件に首を突っ込み、人情深さが災いして最後は気合いと殴り合いでケリをつけるという“時代遅れのオッサン探偵・連城新次郎”を熱演。「1972年の映画『ロング・グッドバイ』をイメージした」という井川広太郎監督に本作に込めた思いとともに、キャラクターが際立つ映画の魅力について話を聞いた。

あらすじ:寂れた街の喫茶店を事務所代わりにしがない探偵業を営む連城新次郎(北村)は、闇の賭博場でトラブルを起こし、顔なじみのヤクザである笠原組幹部の恭一(松角洋平)から面倒な仕事を押しつけられる。それは笠原組が敵対する中国系マフィア、バレットの関与が疑われる放火事件の調査だった。時を同じくして新次郎は、フィリピン人の両親を強制送還させられた過去を持つミチコ(武イリヤ)から、謎の失踪を遂げた親友のクルド人女性の捜索を依頼される。やがて恭一が何者かによってボウガンを撃たれる事件が発生し、笠原組とバレットの対立が激化。図らずも二大組織の抗争に巻き込まれた新次郎は、全てが複雑に絡み合う一触即発の危機に呑み込まれていく。
キャラクターが際立つ映画を渇望していた
――脚本は『ろんぐ・ぐっどばい 探偵古井栗之助』などの中野太さんと木田紀生さんとなっていますが、井川監督は構想の段階から関わっていたそうですね。
井川監督:そうなんです。実は8年ぐらい前から、「オジサンが活躍する探偵映画を撮りたい」と思って構想を温めていたんですが、プロデューサーの木滝(和幸)さんと一緒に試行錯誤しながらようやく企画がまとまり、最終的な座組も決まってから、中野さんたちに脚本を依頼しました。
――なぜ、オジサン探偵の映画を撮りたいと思ったんですか?
井川監督:8年前なので自分もまだギリギリ若者の部類だったんですが(笑)、「そういえば最近、映画やテレビドラマでしか観れないような破天荒でかっこいいオジサン、いなくなっちゃったなぁ」という思いがなんとなくあって、それがちょっと淋しかったんですよね。オジサン達が活躍する作品はあるにはありますが、結構、物わかり分りのいいキャラが多くて、「そうじゃないんだよ」っていうか、何か物足りなさがあった。結局、企画を練っているうちに8年も経って、自分がおじさんと呼ばれるレベルになってしまったんですが、それでも「やりたい!」という情熱が消えなかったので、これは作る価値があるなと思いました。
――なるほど、キャラクターが際立つ映画がなくて物足りなさを感じていたと?
井川監督:それこそ『あぶない刑事』なんかは内容をほとんど覚えていませんが、タカとユージのことは死ぬまで忘れないじゃないですか。やはり、キャラクターと演じてる俳優の虚実が入り混じった存在に憧れて大人になってきたんだな、という思いがあるわけです。だから、そういうキャラクターを自分も作りたかったというのが大きな理由ですね。そのためには、やはり物語に負けない強い個性が必要で、脚本だけじゃなく、演じる俳優の力もとても重要になってくるわけです。

――1970~80年代の映画・ドラマで育った世代は「待ってました!」という感覚ですが、20代を中心とした若者層の反応などは考えましたか?
井川監督:むしろ、オジサン世代が観て、「これだよ、コレ!」っていうのを作りたかったので、全く考えないようにしていました。ただ、試写などで若い方々の反応を聞くと、意外とすんなり受け入れられていて、「普通に面白かった」「かっこよかった」という感想が多くて、我々が思うほどジェネレーション・ギャップはなく、彼らにとっては「新鮮に観える」というのは、我々のような「懐かしむ」世代にとっては新たな発見でしたね。
――「終末」というタイトルが面白いなと思いました。どんな意味が込められているのでしょう?
井川監督:暴力団対策法とかでいろいろ制限が加えられたことからヤクザが弱体化し、反社会勢力なるものが出てきたわけですが、結構、そういった悪の組織も、連城新次郎ようにそこにまとわりつく人間たちも、みんな一緒に終わりに向かっていってる気がしているんですね。その中でどうやって生きていくのか、どうやって居場所が獲得するのか、という話だと思ったので「終末」という言葉をタイトルに入れました。劇中、それぞれが困ってるし、それぞれが生き残ろうと頑張ってるし、そういった意味では、みんな対等な人達なのかなと自分は思っています。
名優・北村有起哉が主人公に命を吹き込んだ
――主演の北村さんがすごく良かったです。まさにハマリ役。この年代で連城新次郎を演じられるのは、北村さん意外に思い浮かばないくらい自分のものにしていました。これは当て書きだったんですか?
井川監督:どう思われますか?
――いやぁ、どう観ても北村さんに当てて脚本を書かれたような感じがしました。
井川監督:ありがとうございます。当て書ですか?って言われるのが最高に嬉しいですが、実は全く(北村さんを)想定せずに書かれているんです。昔のような熱量を持った俳優さんって誰なんだろうって、脚本が出来上ってからもずっと悩んでいたんですが、ある日、木滝プロデューサーの方から「北村さんがやってくれそうだが、どうだろうか」と言われて。その時は飛び上がって喜びました!

――ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』を参考にされたと聞きました。
井川監督:そうですね。本作を制作するにあたって、「ハードボイルドとは何か?」という議論を準備の段階から北村さんとよくしていて、『ロング・グッドバイ』の話は出ましたね。ハードボイルドって、厳密には別にジャンルとして確立しているわけではないし、すごくフワッとしているものですが、だからこそ挑戦してみたいと。その辺りの思いを共有する意味でも『ロング・グッドバイ』は何度も観ましたし、そのほかにもいろんな作品を観てとことん話し合いました。
――『ロング・グッドバイ』のほかにはどんな作品を参考にされたんですか?
井川監督:「傷だらけの天使」や「探偵物語」『私立探偵 濱マイク』シリーズはもちろんですが、黒沢清監督のオリジナルビデオ『勝手にしやがれ!!』シリーズとかはかなり意識しましたね。それこそ私が一番好きな監督でもあるジョン・カサヴェテスの『チャイニーズ・ブッキーを殺した男』なんかも参考にはなっていると思います。特に「このシーン」という明確なものはないんですが、これらの作品は必ずどこかで影響していると思います。
――この映画では、武イリヤさん(『SUNNY-強い気持ち・強い愛-』『リっちゃん、健ちゃんの夏。』)、青木柚さん(『うみべの女の子』『よだかの片想い』)、髙石あかりさん(『ベイビーわるきゅーれ』『とおいらいめい』)、水石亜飛夢さん(『鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー』『東京バタフライ』)など、新進気鋭の若い役者さんたちを脇役で起用しているところも見どころですよね。特に青木さんが演じた、極端な考え方を持つ若者・佐藤翔が、新次郎に突っかかるところがちょっと面白くて。あれはどういうコントラストというか、狙いがあったのでしょう?


井川監督:主人公の新次郎は、年齢など気にせず、いろんな世代と関わることができる稀有なキャラクターで、そういう中から彼なりの考え方が形成されていったと思うんですが、青木さんが演じた翔というキャラクターはそこが足りてなくて、圧倒的に情報量の方が多く、それに比べて圧倒的に大人と接する機会が少ない。だから、体温を伴った人物造形がし切れていないところが根底にあって、そんな彼とどうすれば触れ合うことができるのか…そこは大人である我々のテーマでもあるのかなと思い、物語の中に入れ込むことにしました。
痛みを共有するアクションにしたかった
――最後に、アクションシーンについても聞きたいんですが、ボウガンやナイフは使いますが、一撃するシーンの描写はなく、基本、素手で殴り合っている。しかも、かっこいいアクションではなくリアルで、時にユーモアがあったりしますよね。
井川監督:そもそも僕は銃が好きじゃないっていうのがありまして…。アクション映画を観る分にはいいんですが、自分が監督として描くときに抵抗があるので避けたいなというのがありました。もう一つは、一方的に相手を叩きのめす暴力にはしたくない。例えば、新次郎は素手で殴って、自分も同じくらい殴られる。彼は喧嘩が強いわけではないのですが、ただ負けない。絶対に負けない。「痛みを共有する」という部分は、アクションを描く時には不可欠だなと思ったんです。
――確かに勝負は五分五分、でも最後に立っているのは新次郎ですね。
井川監督:相手を倒すのが目的じゃなくて、自分も痛みを背負うっていうところですね。自分が昔観たキャラクターにはそういうものがあった気がして。一方的に殴るんじゃなくて、相手にも陰があったり、心に傷があったり、言えない過去があったり、いろんな人生の痛みを背負っている。アクションでそれを表現するときに一方的な攻撃だと成立しないんですよね。やっぱり自分も同じくらい殴られなきゃいけないと思うんです。
――ワンカット長回しを随所に使っているのは、その人間味溢れるアクションシーンによりリアリティーを持たせるためでもあるわけですね?
井川監督:そうですね。先ほどもお話したようにキャラクターと俳優が虚実一体化となるような映像作りをしたいので、カット割りでつないで強い姿を見せるのは違うと思いました。生身の肉体で格闘する姿を観て、「頑張れ!」っていう思いが湧き起るのは、北村さんに対してなのか、新次郎に対してなのか?もはや観客の我々にはわからない…自分が昔観ていたスターって、長回しに耐える人たちでしたし、「こんなに走るのか」ってくらい走っていたし、「危ない!」って思うようなアクションシーンにも果敢に挑んでいたし、やっぱりそういうスターには肉体性が不可欠だと思っていたので、アクション監督の園村(健介)さんにもそう伝えて、北村さんにも無理を承知で頑張っていただきました。

――北村さん、すごい走ってましたね!
井川監督:失礼な話ですが、北村さんがここまでアクションできるなんて知らなかったので本当に驚きました。3分長回しのアクションなんて、何度もできないですよ。ボクシングだって1ラウンド3分が限界ですからね。
――容疑者らしき青年を北村さんが走りまくり、自転車漕ぎまくり追いかける…アングルが『太陽にほえろ!』のようでした(笑)
井川監督:あそこはもう完全に70~80年代の日本のドラマを意識してます。実をいうと一番撮ってみたかったシーンなんですよね。だから、北村さんには新米刑事のように走っていただきました(笑)
――それにしても、新次郎は観るたびに愛着が湧くキャラクターですね。3回観たんですが、まったく飽きなかった。早くも続編が観たい気分です。
井川監督:自分としては、キャラクターが際立つ映画や、スター俳優がハードアクションに挑む姿をもっともっと観たいので、これからもそういう映画をどんどん作っていきたいと思っています。その第一弾がこの作品なので、「続編を期待しています」って言われるとめちゃくちゃやる気が出ます!そういう声がたくさん届くと嬉しいですね。(取材・文・写真:坂田正樹)
◆井川広太郎 監督/プロフィール

1976年生まれ。一橋大学在学中に、野崎歓に師事し映画批評を学ぶ。その後、撮影監督として、白川幸司監督作品『眠る右手を』(2003)などに参加。 2006年、『東京失格』で長編監督デビュー。2012年、今泉力哉、福島拓哉、吉田光希の3人の監督によるオムニバス作品『ヴァージン』の一編で脚本を担当。2015年に監督・脚本を担当した『キミサラズ』を発表。
2022年12月16日(金)よりシネマート新宿にて公開中、全国順次公開
©2022「終末の探偵」製作委員会