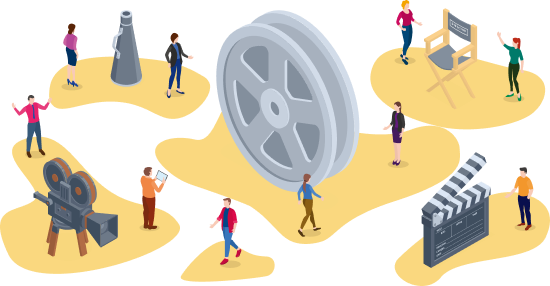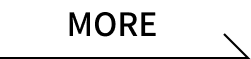1999年公開の映画『アメリカン・ビューティー』で作品賞を含む5部門でアカデミー賞®️を受賞し、一気にその名を世界に知らしめたサム・メンデス監督。その後も、アカデミー賞®️6部門にノミネートされた『ロード・トゥ・パーディション』(02)、レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットの『タイタニック』コンビを復活させた『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』(09)、さらにはダニエル・クレイグとタッグを組んだ007映画2作『007 スカイフォール』(12)、『007 スペクター』(15)、ワンカット撮影が話題となったアカデミー賞®️10部門ノミネートの『1917 命をかけた伝令』(20)と、幅広いジャンルで傑作、話題作を次々と世に送り出してきた。そして今回、満を持して自身の少年時代の思いを投影した自伝要素の強い作品『エンパイア・オブ・ライト』を発表。再びアカデミー賞®️ほか世界の映画賞、映画祭から熱い視線を浴びているが、今、なぜ、私小説的映画に取り組んだのか。メンデス監督本人に本作に込めた思いを聞いた。
ーー映画館を舞台にしたこの物語を書くきっかけは何だったのですか。
メンデス監督:心の片隅に、「脚本の全編を一人で書いたことがまだないな」という思いがありました。ですから、ロックダウンの最中に書き始めました。子供の頃から心に焼き付いている思い出を下敷きにしています。この映画の本当の動機は、目の前で精神が錯乱する人を見て育ったという事実です。精神的な病が周期的に発症する様子をずっと見てきました。ヒラリーの土台となっているのは一緒に暮らしていた私の母親です。私はほんの子供でした。長いあいだ、周期的に発作が起きても、私と母には成す術もありませんでした。私はその発作の時期をやり過す方法をいつも探していました。

10代の頃からずっと心に引っかかっているもう一つのことは、当時の人種政策です。それが私の政治的な見解を形成しました。1980年代初頭のサッチャーの時代に育ちました。イノック・パウエルもいましたし、ナショナルフロントの台頭、ブリクストンの暴動、ニュークロスの大火災もありました。ですが、同時に、当時の英国の音楽界は、健全な人種的多様性がある驚異的な時代でした。2トーン・レコードのスカ、ザ・スペシャルズ、ザ・ビート、ザ・セレクターが人気でした。
私の心に残るこの二つの若き日のしこりが重なり、胸が熱くなりました。そして、私にとっては映画館が、この映画の登場人物と同じように、暮らしの憂さから逃れられる場所でした。この映画は映画への賛歌だ、と言う人もいますが、それだけではありません。映画というものが、挫折したり、落ちこぼれたりした人を再び立ち上がらせる力があることを表しています。ヒラリーも スティーヴンもそれぞれの理由で社会からはみ出しています。少なくとも、本人たちはそう感じています。
ーーなぜ今がこの映画を発表するのに絶好のタイミングだと思ったのですか。
メンデス監督:ロックダウンと感染拡大の時期のあいだに、誰もが感じていた心もとなさに呼ばれたと思います。一人で過ごす時間が丸一年もできたので、やり残していたことをやろうと考えました。 無駄に過ごすことはできません。ロックダウンの状態が毎日続くわけですから。私の場合は、ずっと葛藤していた、あるいは呪われていた、子供の頃からの思い出に手をつけ出しました。書くことで、この思い出を昇華させようとしたのです。そして、ロックダウンの最中に世界規模で人種差別への報いが起きました。巣ごもり生活のなかで、我々の人種政策がどのように形成されたのか、世界は進歩する努力を忘れていないかを静かに振り返りました。

それとまた全く別のことで、職業に関わらず、誰もが心配していたことがあります。人生を賭けていたものが、一夜にして消えてしまうのではないかという不安です。私の場合は、映画館であり、劇場であり、生で観てもらうパフォーマンスのことです。暗がりの中に他人同士が並んで座り、物語が繰り広げられるのを一緒に見る、という体験がもうかなわなくなるのではないか、という恐怖です。無くなって、初めてその幸せに気づくことになるのでは、という恐れです。
ーー今作では初めて自ら脚本を書きあげました。取扱いが難しい複雑なテーマであり、物語の各要素は、登場人物の生きてきた歴史に忠実です。お客さんから共感を得られる自信はありましたか。
メンデス監督:演劇の演出で学んだことは、様々な要素やニュアンスに、時には不協和音にさえ、恐れをなさないということでした。シェイクスピアやチェーホフの手法に今すぐ戻るべきです。この映画は物語の途中から始まります。見る者は、長い間続いている人間関係を見定めなくてはなりません。ヒラリーは見るからに謎めいていて、それが徐々に解き明かされていきます。他の人物にもそれぞれ違った個性があります。

この映画の様々な要素が、観かた次第で、違う意味を持って見えることを願います。そのようにできたのは、本能もありますが、数々の卓越した脚本家とタッグを組んできたからです。舞台だけではなく、映画ででもです。私のデビュー映画『アメリカン・ビューティー』の脚本は素晴らしく、まさにこの見え方になりました。本作と映画のスタイルは全く違いますが。
ーー映画撮影でも舞台のようにリハーサルを欠かしません。起用した俳優は、どのようにして、この個性あふれる出演者陣の中で、自分の立ち位置を見つけていくのでしょうか。
メンデス監督:歳を重ねるごとに、予定調和な演出が、ますますイヤになってきました。上手い俳優にスタジオに入ってもらい、自由に解釈してもらうようになりました。 映画撮影は、舞台とは違い、必要以上に上下関係を重視します。ですから、そのしきたりをちょっと横に置いて、グループになるのです。見えない何かに向かって、それぞれのアプローチを試みます。でも、目指しているものは同じです。試行錯誤し、到達点がどこかを明らかにし、グループとしてそれを達成しようとします。

この脚本を書くまで、俳優にこれほど感謝したことはありませんでした。文字を机上でひねり出すのはひとつのことで、俳優が個々の弱みを持ちながら、血の通った実在の人物として、脚本を具現化するのはまた別のことだからです。これは誰にでもできることではありません。オリヴィアとマイケルだけではなく、ニール役のトム・ブルック、ノーマン役のトビー・ジョーンズ、ジャニーン役のハンナ・オンズロー、デリア役のターニャ・ムーディも重要なのです。ターニャは移民という歴史を背負いながら、息子を育て上げてきた女性を演じます。ターニャは、見事にデリア役に命を吹き込みました。他の俳優にも同じことを感じました。
ーー自分を投影したことを脚本化するのは不安があったと思いますが、結果的にはやってよかったと思えましたか。
メンデス監督:思っていたより、ずっと難しかったです。ですから、敬愛しているコーエン兄弟やポール・トーマス・アンダーソンやウェス・アンダーソンのような、脚本のアイデアが豊富で、何度も推敲し、撮影に入っていく監督たちを改めて素晴らしいと思いました。脚本は映画を撮ろうとするときに、いつも飛び板として存在していました。どんな映画でも、足跡を残しながら制作が進行します。準備、撮影、編集の段階でその足跡を越える度に、映画の形が定まっていきます。でも、その足跡が自分の子供時代の家に連れていき、本当は入りたくない2階のあの部屋に導くなら、楽しい気持ちにはなれません。

ですが、やった甲斐がありました。近年の半自伝的、自伝的な映画に触発され、私自身の物語を語るべきだと感じていました。『ROMA/ローマ』のような映画をイメージしました。本作とは全く違いますが、とても美しく、もっとストレートに自伝的です。本作では、私の過去のいろいろな苦い思い出を利用しています。それらを様々な方法で組み合わせています。本当にやってよかったと感じています。撮影の余韻が収まるまで、どんな映画になったかよく分からないかもしれません。まだ、落ち着いた気持ちで、客観的に見ることができません。
ーーストレートに自伝的ではなくても、ある程度の勇気は必要でしたか。
メンデス監督:普通の映画10本分の勇気が必要でした。理由があります。映画として成立するのか、脚本は大丈夫か、個人的なことをさらけ出せるのか、といった様々な角度から、自分に勇気があるのか確かめるのに時間がかかりました。こうしたことを、どうすれば実現できるか熟考しなくてはなりませんでした。
ーー本作では、エンパイア劇場が崩れる映画の宮殿として描かれます。コロナのあいだの映画館が封鎖された状況や、演劇に関する昨今の議論を考えると、本作の公開はまさにいいタイミングだと思えます。
メンデス監督:怖いのは、調査を進めるなかで、海辺の町の状況を見てみると、戦後ブライトンには一時期40の映画館があり、1980年代でも18館くらいはあったのが、今やたったの4館か5館になっていることです。ブライトンは大きな町なのに、です。

マーゲイトでは、映画館、エンパイア劇場のロケーションとなったドリームランドだけが現存していますが、もう映画館ではなくなっています。心に残る出来事がありました。ロケハンに出かけた時、雪の中で震えながら私のサインをもらおうと待っている二人の熱心なサイン蒐集家がいました。その一人が言いました。「メンデスさん、私はあなたの大ファンです。『アメリカン・ビューティー』をこの映画館で4回見ました。」この言葉に、ああ、この映画館は、時の移ろいと共に、非日常的な体験を求めて地元の人々が集まる華やいだ場所から、ビンゴホールへと変わり、今ではそれも廃墟と化しているのだ、と痛感しました。
この映画によって、私が愛する映写技術をドラマにすることもできました。フィルムでの撮影が廃れていくことがよく言われますが、私にとっての大きな喪失は、映写技術のほうです。映画を観客に映してくれる映画技師が、いつもあの暗闇の先にたった一人でいてくれている、という感覚の喪失です。

映画を取り扱う時に必要な細心の注意、丁寧さ、映画史への敬意、こうしたものはどれもなくなりました。もちろん、もっと効率的なものに取って代わりましたが。映画界は大きな危機に面し、妥協を迫られている、とまでは言えません。ですが、魔法を失いました。映画の魔法が消えたことは確かです。映画館がなくなろうとしているわけではありません。映画館は決してなくなりません。ですが、映画館は変化のさなかにあります。映画館で映画を見るという行為が格別であるのは、人間同士が同居できる環境をお互いに築いているからだと私は考えています。椅子席とロビーと売店だけがあればいいのではありません。そこは、お客さんが丁重にもてなされ、劇場スタッフは規則正しく立ち振る舞い、驚異の音響と映像を備えた娯楽の殿堂なのです。これぞ映画館であり、映画の成せる美徳なのです。巨大な部屋に映画を見るために見知らぬ人々が集まる、という魔法をかけ続けられるかどうかは、私たち自身の努力にかかっていると思います。

2023年2月23日(木・祝) TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.