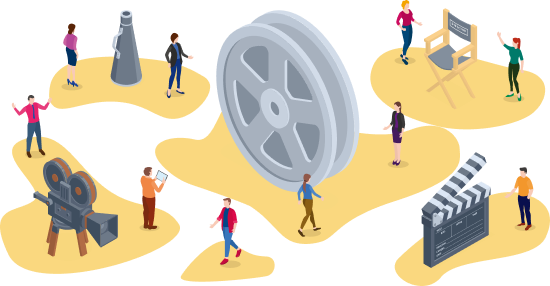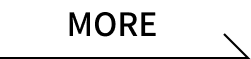ウディ・アレン監督の映画愛がつまった至福のロマンティック・コメディ『サン・セバスチャンへ、ようこそ 』がいよいよ日本劇場公開される。第68回サン・セバスチャン国際映画祭オープニングを飾った本作の舞台裏をウディ監督自らが語ったインタビューが到着。併せて日本のファンに向いて貴重なメッセージ映像も公開された。

<Interview> 本作の舞台は、オープニング作品にも選ばれた、ずばりサン・セバスチャン国際映画祭(毎年9月に開催)。 これまでにローマ、パリなど、大都会の街を舞台に映画を撮ってきたウディ監督は、今回、スペインのサン・セバスチャンを選んだ理由について、「きっかけは、(知り合いの)スペイン人からスペインで映画を撮ったら資金を調達します、という申し入れの連絡があったことです。これまでバルセロナ、オビエド、アビレスで撮ったことがあり、サン・セバスチャンも大好きな街だったので、ぜひそこで撮りたいと思いました。気候も温暖で、人も食事も素晴らしい。撮影に入ればそのロケ地に数週間滞在することができる…それも決め手の一つでしたね」 と振り返る。また、劇中に出てくる9本の名作クラシック映画を選んだ理由を尋ねると、「私のお気に入りの映画の中から、『映画祭を舞台にした映画を撮る』という構想に最も適したプロットの作品を選びました」とモノクロームで描く映画ファン垂涎のオマージュ・シーン(ルイス・ブニュエル監督作『皆殺しの天使』やフェデリコ・フェリーニ監督『8 1/2』、クロード・ルルーシュの『男と女』などなど)についても明かしてくれた。

これまで何度かウディ作品に出演し、今回、主人公モートを演じたウォーレス・ショーンを主役に配した理由については、「可笑しかったり、傷つきやすいキャラクターをきちんと体現できる素晴らしい俳優ですよね。そもそも知的な人なので、非常に共感もできます。最初は別の人を考えていたけれど、彼の名前が上がったとき、ピンと来たし、演じていてパーフェクトだなと思いました。彼と一緒に仕事をするのは楽しいし、仕事がしやすいし、クリエイティブな方ですね」と、ウォーレスにゾッコンの様子。

今作で4作目となる撮影監督のヴィットリオ・ストラーロとのコラボレーションについても、「歴代の映画撮影監督の中でもヴィットリオは天才と言えます。彼自身もたくさんのアイディアを持っていて、一緒に仕事をしていて楽しいです。撮影前に映画のアプローチ、視覚的な構想というのを話し合い、ストーリーに即したシネマ的な面を実行し、そしてそれをスタイリッシュな方法で実現できるのがヴィットリオなんですね」と絶賛した。

<Story> かつて大学で映画を教えていたモートは、今は人生初の小説の執筆に取り組んでいる熟年のニューヨーカー。そんな彼が映画業界のプレス・エージェントである妻スーに同行し、サン・セバスチャン映画祭に参加する。ところがスーとフランス人の著名監督フィリップの浮気を疑うモートはストレスに苛まれ、現地の診療所に赴くはめに。そこでモートは人柄も容姿も魅力的な医師ジョーとめぐり合い、浮気癖のある芸術家の夫との結婚生活に悩む彼女への恋心を抱く。サン・セバスチャンを訪れて以来、なぜか昼も夜も摩訶不思議なモノクロームの夢を垣間見るようになったモートは、いつしか自らの“人生の意味”を探し求め、映画と現実の狭間を迷走していくのだった…。
<Staff&Cast> 脚本・監督:ウディ・アレン /撮影監督:ヴィットリオ・ストラーロ/出演:ウォーレス・ショーン、ジーナ・ガーション、ルイ・ガレル、エレナ・アナヤ、セルジ・ロペス、クリストフ・ヴァルツ/2020年/92分/スペイン・アメリカ・イタリア/英語・スペイン語・スウェーデン語/カラー・モノクロ/ビスタ/原題:Rifkin’s Festival/日本語字幕:松岡葉子/提供:ロングライド、松竹/配給:ロングライド

© 2020 Mediaproducción S.L.U., Gravier Productions, Inc. & Wildside S.r.L.