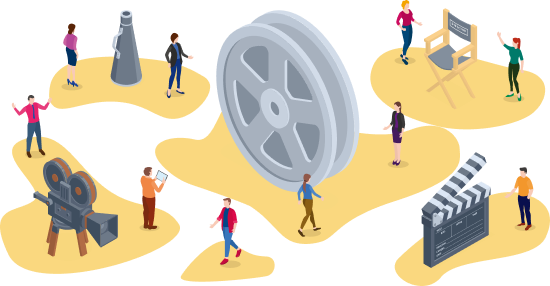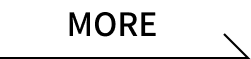都内・本屋B&Bで行われたトークイベントに、白石和彌監督、美術の今村力、編集の加藤ひとみが登壇し、衝撃的な撮影秘話を語った。
今村、加藤ともに、白石監督の長編デビュー作『ロストパラダイス・イン・トーキョー』(10)から白石組に関わる欠かせない存在となっているが、お互いの関係性を尋ねられると、白石監督は「(今村に対して)美術をやりながら映画を一緒に作る人。作品の根底から一緒にアイデアを出して作品の世界観を作ってくれる。その映画的嗅覚に惚れ続けている。(加藤に対して)脚本は理詰めでやっていくところがあるが、編集は理詰めじゃない。加藤さんの編集はこういう画があるからこのシーンは後にした方がいい、という感覚的な部分と理屈の部分をバランスよく持っていて、そこに助けられている」と信頼を2人に伝えた。

トークテーマは、本作のロケ地から始まった。
榛村の自宅は、コロナ禍での撮影延期を経た後の最初のロケハンで見つかったという。白石監督は「ここを見つけてこの映画の方向性がほぼ決まった」と語るほど、素晴らしいロケ地だったと明かした。家の近くに水門があったことで、榛村が川に花びらのようなものを散らす冒頭のシーンを水門で撮るアイデアが現場で生まれたエピソードも披露。今村も完成した作品を観て、「ドキドキした。良い映画を観てるぞという気になった。それぐらいロケ地として完璧」と高く評価した。

燻製小屋についても、今村のこだわりが多数込められた作りとなっている。小屋で行われる惨劇を際立たせるために、小屋の脇に、白い百合を植えたことや、室内の装飾で拷問に使われるフックを鉄工所に特注で作ってもらったなどの裏話が語られた。白石監督は「今村さんの美術の特徴は、真ん中に切り取りづらい柱を置いたり、狭かったりと、どうやって撮影したらいいのってなるのを作ってくれる」と語り、燻製小屋もカメラマン1人入るのがギリギリの狭さだったと撮影の苦労話を笑いながら告白。一方で、白石監督は今村の美術を「どの方向にカメラを向けても絵になる。心強さをいつも感じている」と全幅の信頼を寄せていることを語った。

テーマが編集に移ると、本編中の映像を取り上げ、加藤による解説がなされた。
榛村の水門でのシーンと、祖母が火葬されるのを雅也が見る火葬場のシーンの2つが交互に織り交ぜられたオープニングについて、加藤は「時間軸が異なるため、脚本上はシーンが分かれていたが、榛村の過去の行動が現在の雅也に影響を与えているという2人の関係性を感じさせたかった」という編集の意図のだとか。白石監督は、加藤から送られてきたオープニングを撮影現場で他のスタッフに興奮しながら見せたことを明かした。さらに、雅也が事件の被害者たちの写真を壁に貼っているシーンや犯行現場を訪れるシーンでは、過去の事件の話が展開される中で、フラッシュバックのように拷問のシーンをインサートすることで、緊張感を途切れないようにしたと狙いを語った。また、加藤は撮影現場を見ていないため、送られてきた素材を見て驚くこともあるという。中でも、面会室の“ある”シーンは本当にびっくりしたと述懐。脚本上に無かった演出や動きが現場で生まれてくることに「現場のひらめきは面白い、映画が生き物であることを感じる」と語った。

最後に、白石監督は「スタッフにやりたいことをまずやってもらう、どう楽しくやってもらえるかを考えるのが自分の仕事。今日2人の話を聞きながら発見もあった。他のスタッフの話も聞いてみたい」と感想を述べ、トークイベントを締めくくった。
日本劇場公開:2022年5月6日(金)より全国公開中
©2022映画「死刑にいたる病」製作委員会