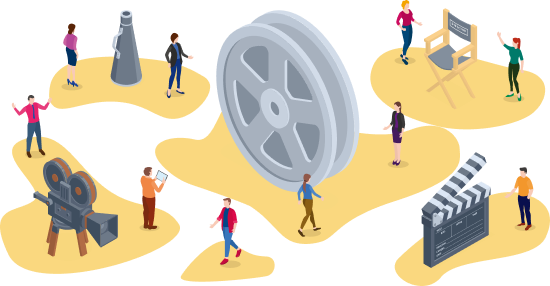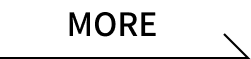松山ケンイチと長澤まさみを主演に迎え、事件が絶えない介護の問題に鋭く切り込んだ衝撃作『ロストケア』(公開中)。介護士でありながら42人を殺めた殺人犯と、彼を裁こうとする女性検事が、それぞれの“信念”をもとに魂をぶつけ合う凄まじい攻防が、観る者の感情を激しく揺さぶる。これまで、さまざまな社会問題を軽やかに、かつ印象的に描いてきた前田哲監督が、胸に突き刺さるようなアプローチで挑んだ本作を改めて振り返った。

あらすじ:ある日の早朝、民家で老人と訪問介護センターの所長の死体が発見された。 捜査線上に浮かんだのは、センターで働く斯波(しば)宗典(松山)。だが、彼は介護家族に慕われる献身を絵に描いたような男だった。検事の大友秀美(長澤)は、斯波が勤めるその訪問介護センターが世話している老人の死亡率が異常に高く、彼が働き始めてから死者が 4 0人を超えていることを突き止める。真実を明らかにするため、 斯波と対峙する大友。すると斯波は、自分がしたことは『殺人』ではなく『救い』だと主張する…。
●さまざまな社会問題に対して映画人ができること
――年老いた親を持つ身として、本作を拝見させていただき、いろんなことを考えさせられました。前田監督の作品は社会問題を扱った映画が多いのはなぜでしょう。
前田監督:ひと言で言うと、エンタメから一番遠いものをエンタメにしたいという思いがあるんですね。『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の介助者と障がい者の人間味溢れる関係性もそうですし、『ブタがいた教室』では当時まだ知られていなかった“食育”のことを取り上げました。もちろん、いじめや虐待なんかもそうですが、いろんな社会問題を僕らは新聞やネットニュースで目にすることはありますが、見出しだけ読んで中身を読まないことと同じで、その先の一歩がなかなか踏み出せない。
そういった状況の中で、僕に何ができるのか。そう考えた時に、僕は映画を作る人間なので、作品を通して声を上げていくとことになる。ただ、あまりにもメッセージ性が強く重たい作品だと人は観ようとはなかなか思わない。観たいと思ってもらうことが大切で、観てもらって「面白い映画だったね」「役者が素晴らしかったね」という感想の中に、「あれ?あの問題は…」と少しでも観客の心の中に残ってくれることを目指しています。

――今回、第 16 回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した葉真中顕さんの小説を映画化しようと思ったきっかけは何だったのですか。
前田監督:僕の両親は施設に入っていますが、介護の問題は当事者だけでは抱えきれないものがあるんですよね。葉真中さんの原作は僕にとってかなり衝撃的で、いい意味での正義感というか、国や行政に対する憤りが物凄く強かったので、それをエンタメに落とし込んで、より多くの方々に届けたいと思いました。もちろん、小説でも十分に伝わると思いますが、映像は、ファンタジー的な要素も入れられるので、より広がりが出るというか、親しみが湧くというか。僕は映像で語る物語は人の心に残るものだと思っているので。
――それにしても、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』や『老後の資金がありません!』などの印象が強く、コメディータッチが前田監督の真骨頂だと思っていたので、本作の胸に突き刺さるような演出には驚きました。
前田監督:これまで携わってきた作品のイメージから、前田哲=明るい映画を連想される方も多いでしょうが、確かにユーモアを取り入れてハッピーな作品にしたいという思いは常にありますが、それも映画の題材次第なので、今回は緊張感のあるシリアスな表現を選択しました。僕が言うのもおこがましいですが、あのビリー・ワイルダー監督(『お熱いのがお好き』『失われた週末』など)だって、コメディーだけじゃなくてシリアスな作品も作っていますが、“人間を描く”ということに変わりはないですからね。
●松山ケンイチvs長澤まさみはこの映画の肝
――松山さん演じる介護士の斯波と、長澤さん演じる検事の大友が、信念と信念をぶつけ合いながら対峙するシーンは、魂を揺さぶられました。撮影現場はどのような雰囲気だったのでしょう。
前田監督:松山さんと長澤さんが対峙するシーンは、この映画の“肝”になると感じていたので、シンプルに二人の芝居をしっかり撮れば伝わるなと思いました。もちろん、二人がそれぞれのセリフを全身全霊で魂の叫びのように出し切ってくれたことは言うまでもありませんが、とてもいいシーンになりましたね。

――企画を立ててから映画化まで10年かかったそうですが、その間、脚本もかなり練り直したのでしょうか。
前田監督:なかなかこの企画が通らなくて、最初に3パターン書いて、そのあと 20稿以上、脚本の書き直しをしました。原作には、もう一人、老人を食い物にしていくアウトローのような人物が出てくるんですが、今回、映画化するにあたってその人物は登場させず、介護士と検事の対決にしようと。しかも、原作では男同士の戦いでそこに奇妙な友情が生まれるんですが、それもやめて検事を女性に変えて、徹底的に対峙する構図の方が強くエンタメ的になると考えました。
――松山さんは企画の段階から参加していたそうですね。
前田監督:柄本明さんもおっしゃっていましたが、誰もが認める実力派、松山さんの演技は抜群だと。映画『ドルフィンブルー フジ、もういちど宙(そら)へ』以来、「また一緒にやりたいね」と互いに連絡を取り合っていたんですが、この原作を読んだタイミングにちょうど連絡があって、これは運命だなと思い、企画の段階から参加していただきました。ただ、そうなってくると、松山さんに対抗できる女優さんを誰にするか?ということが問題になってくるんですが、今だったら長澤さんしかいないだろうと。長澤さんご自身も「松山さんと向き合った芝居がしたい」という思いがあったらしく、快く受けてくださいました。その意気込みが画面に出ていますよね。

ただ、僕と松山さんは企画の段階から10年間、ずっと話し合ってきた仲なので、現場でわからないことは少なかったですが、今回初めての長澤さんとは、よく話し合いを重ねました。毎シーン、毎カットごとに悩み、苦しみ、考え、監督である僕に逐一相談しながらも、自分自身の気持ちをコントロールして徐々に大友の気持ちにシンクロさせていった感じでしたね。凄い女優さんだと思います。
――実際の検事さん、あるいは介護士さんを取材されたりもしたんですか?
前田監督:長澤さんは同年代の元検事さんと会っていろいろお話を聞いていましたし、松山さんは現場で現役の介護士さんから付きっきりでアドバイスを受けていました。コロナ禍でなかったら、実地でやる予定だったんですが、それができないということで、いろいろサポートしていただきながら役づくりをしていったんですが、長澤さんの演技を観た弁護士さん、元検事さんが、「明日にでも裁判に出れますよ」と絶賛していましたね。本人は、「大丈夫かな」とか、「あの時の動きはあれでよかったかな」とか、ずっと心配していましたが、僕は撮っている時から「いける」と確信していました。

●主要人物の詳細な履歴書を作ることが大切
――描き方を間違えると、加害者がサイコパスに観えてしまう危険性もあったと思いますが、柄本明さん演じる認知症の父親との壮絶な日々を、目をそらさずしっかりと描き、斯波のキャラクターを深掘りしていたところが素晴らしかったです。
前田監督:原作では、自分の感情をも封印して、淡々と殺人を犯していくんですが、 僕は映画の中ではそういう風には描きたくなかった。苦しみもがいてたどり着いた自分の“信念”を持っている斯波が、被害者一人ひとりに対して本当は命を断つことなどしたくないのに…、その苦しみを感じながら犯行におよんでいる、という描き方にしたかったんです。
――松山さんと柄本さんの“戦い”も凄まじいシーンでした。
前田監督:あのシーン、実は2日間で撮ったんですが、言葉は悪いですが、柄本さんが化け物のような芝居をしてくれました。認知症が徐々に進んでいく段階も繊細に演じられて、息子役の松山さんがどんどん追い込まれ、頭が真っ白になっていくんですが、とても2日間で撮ったとは思えない濃厚で残酷な時の流れを体感させてくれましたね。

――冒頭で、コメディーの印象が強い前田監督の意外な演出に驚いた…というお話をしましたが、これはもちろん題材もありますが、主人公のパーソナリティーだったり、歩んできた道のりだったり、それによって培われたバックボーンだったり、そういった“人物描写”が核としてしっかりあるから、そのキャラクターによっておのずと作品のテイストが変わってくるのかなと思いました。
前田監督:確かにバックグラウンドは大切ですよね。一番脚本作りで苦労したのは、実は松山さん演じる斯波よりも、長澤さん演じる大友のバックグラウンドだったんです。原作は男性で家族もいたんですが、今回は母親だけの関係に絞り、その過程でシングルマザーにするとか、いろいろ考えました。問題は斯波も含めて登場人物が何を背負って生きてきたか。これを具体的に出す、出さないは別として、その設定によって芝居のリアクションも変わってきますからね。
――確かに、松山さんの方は可視化されていましたが、長澤さんの方はリアクションで自身のバックグラウンドを感じさせる芝居が多かったですね。
前田監督:これは助監督時代にずっとやってきたことなんですが、メインとなる登場人物が生まれてから今日までの履歴書を作るんです。脚本を書く時にもちろん考えますが、ザックリしたものなので、助監督が詳細に作るんです。何年何月に生まれて、子供の頃に何があったとか、どんな家庭で育ったとか、エピソードまで細かく考えて、それ俳優に渡すんですね。参考にしてくださいと。今は助監督に作ってもらい確認する立場になりましたが、この作業は欠かさず続けています。
――今、助監督時代のお話が出ましたが、一番影響を受けた監督、あるいは監督から学んだこと、いただいた金言などあれば教えていただけますか?
前田監督:一番影響受けたのは、伊丹十三監督と滝田洋二郎監督ですね。伊丹さんからは、映画に決まりはない、なんでもあり、自由である」ということを教えていただきました。例えば、『マルサの女』なら、お金を入れるバッグというと黒が定番ですが、それを赤と白のストライプの紙袋にするわけですよ。「その方が目立つだろう」と。あるいは、ワンシーンしか出れない俳優とかいるじゃないですか。そうすると、顔全面にアザを作って印象に残るように演出したりするわけです。一方、滝田さんは、俳優が嫌がることを絶対にしないんですよね。俳優を乗せて、気持ちよく演じさせることを教えていただきました。
――お二人から学んだことが、本作も含め前田監督の作品に生きているわけですね。
前田監督:もちろんそうですね。お二人の存在は凄く大きかったです。
(取材・文・写真:坂田正樹)

【主な監督作品】 オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』(98)『GLOW 僕らはここに…。』(00)『sWinG maN』(00)『パコダテ人』(02)『棒たおし!』(03)『ガキンチョ・ROCK』(04)『パローレ 甘い囁き』(04)『陽気なギャングが地球を回す』(06)『ドルフィンブルー フジ、もういちど宙(そら)へ』(07)『ブタがいた教室』(08)『猿ロック THE MOVIE』(10)『極道めし』(11)『王様とボク』(12)『旅の贈りもの 明日へ』(12)『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(18)『ぼくの好きな先生』(19)『そして、バトンは渡された』(21)『老後の資金がありません!』(21)など。公開待機作に『水は海に向かって流れる』(23 年 6 月公開予定)、『大名倒産』(23 年 6 月 23 日公開予定)がある。
<Staff&Cast> 出演:松山ケンイチ、長澤まさみ、鈴鹿央士、坂井真紀、戸田菜穂、峯村リエ、加藤菜津、やす(ずん) 、岩谷健司、井上肇、綾戸智恵、梶原善、藤田弓子、柄本 明/原作:「ロスト・ケア」葉真中顕 著/光文社文庫刊/監督:前田哲/脚本:龍居由佳里、前田哲/主題歌:森山直太朗「さもありなん」(ユニバーサル ミュージック)/音楽:原摩利彦/制作プロダクション:日活 ドラゴンフライ/配給:日活 東京テアトル/公式サイト:lost-care.com