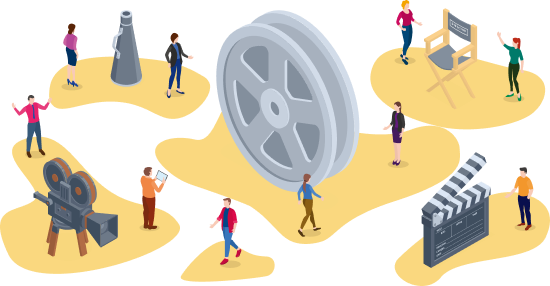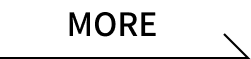カンヌ国際映画祭コンペティション部⾨監督賞受賞をはじめ、国内外の映画祭で高い評価を獲得した鬼才パク・チャヌク監督最新作『別れる決⼼』(2⽉17⽇より公開中)。過激な暴力描写を極力抑え、サスペンスとロマンスが溶け合う禁断のメロドラマに挑戦した本作は、チャヌク監督の演出における新境地もさることながら、『お嬢さん』『渇き』などで長年タッグを組んできた名手チョン・ソギョンの秀逸な脚本に大きな注目が集まっている。「私はメロドラマを書けるほど独自の恋愛観は持っていない、だから今まで避けてきた」というソンギョンが、なぜ苦手な分野にチャレンジし、しかもこんなにも狂おしい愛憎劇を生み出せたのか?その舞台を聞いた。

本作は、アン・リー監督作『ラスト、コーション』(07)のヒロイン役で⼀躍国際派⼥優として注目を集めたタン・ウェイと、『殺⼈の追憶』(03)、『グエムル ~漢江の怪物~』(06)などポン・ジュノ監督作品で名を馳せたパク・ヘイルが繰り広げるラブサスペンス。ある日、崖から男が転落死し、他殺と見たヘジュン刑事(パク・ヘイル)は、被害者の妻ソレ(タン・ウェイ)を容疑者として調査を開始する。だが、取り調べが進むうちに、お互いの視線は交差し、それぞれの胸に⾔葉にならない感情が湧き上がってくる。いつしかヘジュン刑事はソレに惹かれ、彼⼥もまたヘジュンに特別な想いを抱き始めるが…。
●オファーを承諾したのは監督を救うため?!
――チャヌク監督といえば、過激なバイオレンス描写のイメージが強いですが、本作では刑事と容疑者が織りなす“禁断の恋”に重きを置いています。映画作りにおいて、何か心境の変化があったのでしょうか?
チョン・ソギョン:暴力描写というのは、観客がそのシーンを観た瞬間、恐怖に慄(おのの)いたり、嫌悪感を覚えたり、感情移入ができるんですね。つまり、映画の作り手と観客がすぐに緊密な関係を築けるという利点がある。そういった意味で、チャヌク監督の作品はこれまで過激な暴力描写がとても多かったと思うんですが、本作ではおっしゃるようにそういったシーンはかなり抑えられています。多分、いろいろと経験を積み重ねてきた中で、暴力描写に頼らなくても「観客の心を捉えることができる」という自信がチャヌク監督の中で培われてきたんだと思います。

――ソギョンさんは最初、脚本のオファーを断ったそうですね。それはなぜですか?
チョン・ソギョン:チャヌク監督が『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』(18)というドラマをイギリスで撮っていた頃、現地に遊びに行ったことがあるんですが、その時に、「ある刑事の管轄区域に、殺人容疑のかかった一人のミステリアスな女性が現れる、という作品を一緒に作らないか?」と提案をしてくださったんですね。でも私は、『渇き』(09)に似ているところがあると思ったので、一度はお断りしたんです。ところが、久しぶりにお会いした彼の姿が、これまで私が見てきた中で、(精神的に)一番つらそうに感じて…「これはいけない」と思い直してオファーを受けることにしました。なぜなら、チャヌク監督の場合、脚本を書くと非常に精神状態が良くなるということがわかっていたから。つまり、“シナリオセラピー”が彼にとって一番の良薬なんです。
●苦手なメロドラマに挑んだ理由
――シナリオセラピーがきっかけだったんですね!それは意外でした。ただ今回は、暴力描写を極力抑えたミステリー仕立てのメロドラマ。ソギョンさんにとっては新たな領域への挑戦になったのではないでしょうか。
チョン・ソギョン:そうなんです。今だからお話しますが、実は私がこのプロジェクトを一度お断りした理由のもう一つが、メロドラマに自信がなかったからです。なぜかというと、私の中に明確な“恋愛観”がないからです。私は気持ちをストレートに出す人間なので、相手のことを好きになったら「好きです!」とはっきり言いますし、逆に好きな相手がそう告白してきたら、素直に受け入れます。結婚もすんなりできましたし、子供も産まれて今も仲良く過ごしています。ですから、お互いの気持ちを探り合ったり、些細な気持ちのすれ違いで喧嘩をしたり…なんというか、恋愛中の男女特有の不安定な気持ちを描くことが、私にとってはとても難しく思えたんです。

――それも驚きです。私はこの映画を観て、ソギョンさんは、恋愛マスターだと思っていましたから(笑)
チョン・ソギョン:いえいえ(笑)。今回、「挑戦できるかもしれない」と思ったのは、交錯する男女の思いがこんな私にも理解できると思ったからなんです。主人公の二人は、とにかく仕事が大好きですよね。特にヘジュン刑事は、事件にのめり込んでいますし、食事中も頭から離れない。なんとか真相を突き止め、解決しようという執念を感じます。でも、見方を変えれば、そこまで事件に没頭できるということは、犯人のことを愛しているのではないかと思えてくるんですね。それが理にかなっているなと思ったのは、狩りをする人(刑事)というのは、やはり獲物(犯人)の気持ちを一番わかろうと努力しているからです。例えば、獲物の逃げ道を必死に予測したり、「きっとここから出てくるに違いない」と待ち伏せをしたり…そう考えていくと、ヘジュン刑事は、ソレの気持ちを一番よく理解していると思うんです。一方、犯人と目されているソレは、自分のした行為を誰にも説明できない孤独な立場ですが、ヘジュン刑事の執拗な捜査を見ているうちに、「この人なら私の気持ちを汲み取ってくれるのでは?」と思い始める…。ですから、ヘジュン刑事とソレが激しく惹かれ合う気持ち、これは成り立つなと思ったわけです。
――悩ましいタン・ウェイさんの存在が素晴らしかったですね。
チョン・ソギョン:私はもともとタン・ウェイさんの大ファンだったのですが、彼女がヒロインを務めてくれるのであれば、苦手なメロドラマも書けると思ったほどです。それくらい大好きでしたので、彼女の事を念頭に置きながらソレというキャラクターを作りました。


●脚本はいつもチャヌク監督との二人三脚
――韓国では、本作のシナリオ集がベストセラー1 位を獲得し、BTS のメンバーRM もSNS や動画サイトで絶賛するなど、今回は脚本も大きな注目を集めました。いつも同じパソコン(やりとりは各自のモニター)でチャヌク監督と作業するとお聞きしましたが、今回も同じやり方ですか?
チョン・ソギョン:今回も同じスタイルです。チャヌク監督と一緒にシナリオを書くときには、作品について二人で徹底的に話し合ったあと、まずシノプシスを書いてみるんですね。そして大枠が出来上がったら、私がそれに沿って脚本を書き進め、チャヌク監督がそれに対して追加をしたり、修正を入れたりして意見を求める。そんなやり取りを何度も重ねながら、あらすじを開発して、どんどん固めていきます。多少の意見の相違はいつもありますが、とても楽しい作業です。私はチャヌク監督と不思議なくらい気が合うんですね。だから、二人で創作する過程をつまらないと思ったことは一度もないです。おそらく脳の構造が似ているのではないかと思います(笑)
――チャヌク監督とともに仕上げた脚本の中でも、本作は完成した映像がとても想像しにくい作品のように思えたのですが、ご覧になっていかがでしたか?
チョン・ソギョン:脚本を執筆している時は、どんな気持ちで最終的にこの映画が終わるのか、全く想像がつかなかったのですが、カンヌ国際映画祭で初めて観た時、ラスト近く、ソレが車を停めた後のシーンからドキドキが止まらず、エンディングまでずっと心が動いていました。チャヌク監督とはもう20年ぐらい一緒に作品を作っているんですが、私が関わった作品の中で、こんな感情を抱いたのは初めてです。脚本家としてではなく、観客の一人として純粋に心を動かされたような、そんな気持ちになりました。観る側と作り手の心を結び付けてくれる…私にとっては本当に大切な作品になりました。

――最後に日本のファンの皆様にメッセージをいただけますか?
チョン・ソギョン:日本の観客の皆さんは、微妙な心理だったり、細かいニュアンスだったり、そういった感情をよく汲み取ってくださると聞いています。公開後、皆さんがどんな反応を見せてくれるのか、とても楽しみにしています!(取材・文:坂田正樹)
2023年2月17日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開中
© 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED